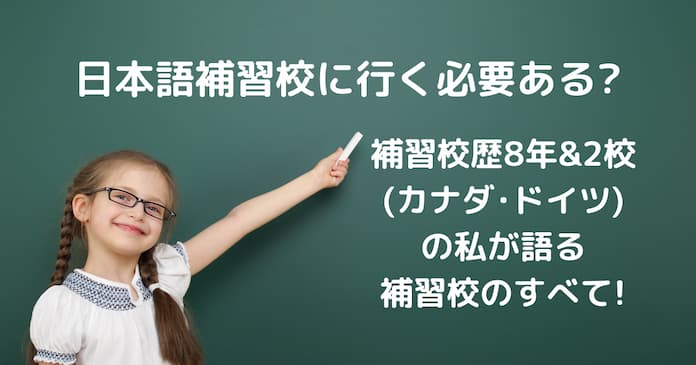こんにちは!フランス在住のKokoです。
 Koko
Koko我が家には、日仏家庭に生まれ一度も日本に住んだことがない子供が2人います(日本の学年だと、長男は高1、次男は中2)。
さて、海外に住んでいる国際結婚家庭のお子さんは、どんなに家庭で日本語教育を頑張っていても、子供が幼稚園や小学校に通い始めるとどうしても現地語が強くなってきますよね。
そんな時、(通える範囲に日本語補習校があるなら)子供を補習校に行かせようかどうしようか、迷われる方もいらっしゃると思います。
うちの子たちは、カナダとドイツで日本語補習校に通いました。
長男が小学1年生で補習校に通い始めてから、毎週土曜日に補習校に通う生活をトータルで8年。
補習校の宿題をやりながら泣いたり、「補習校を辞めたい」と言い出したり、長男は一時期補習校を中断した時期もありましたが、辛かったり悩んだりした時期をなんとか乗り越え、長男は中学2年生まで8年間、次男は小学6年生まで6年間頑張りました。
もし子供たちが補習校に行っていなかったら、我が家の日本語学習はとっくの昔に挫折していたと思うので、私はやっぱり子供たちを補習校に行かせてよかったと思っています。
補習校2校に子供を通わせてみて分かったのが、一言で「補習校」と言っても、各補習校によって、海外赴任家庭/永住家庭(国際結婚家庭)のお子さんの割合、お子さんの日本語(読解力、語彙力、漢字力)のレベル、授業のやり方や難易度、補習校に対して保護者が求めていることなどが異なるということ。
本記事では、補習校について詳しく知りたい方、補習校に子供を通わせようかどうか迷っておられる方のために、我が家の経験を交えながら、補習校とはどういうところなのかご紹介します。



この記事は長いですが、最後まで読んでいただくと、補習校の全体像がよくわかり、お子さんを補習校に通わせるかどうかの判断材料にしていただけると思います!
記事中で「カナダの補習校」「ドイツの補習校」と記載していますが、あくまでうちの子たちが通った特定の補習校の話であり、カナダにある補習校、ドイツにある補習校が、みなそうであるというわけではありません。
そもそも日本語補習校とは? 日本人学校との違いは?


「補習校」と「日本人学校」「継承語としての日本語教育機関」の違い
「補習校」は「補習授業校」と呼ばれることもあります。
「補習校」とは何か?
「日本人学校」「継承語としての日本語教育機関」と比較するとわかりすいです。
- 日本人学校
-
もともと日本人駐在員子女の教育を目的に設立された、平日の全日制の学校。
日本国内の小・中学校、高校と同等の教育課程。日本人学校中学部卒業者は日本国内の高校の入学資格を得られ、日本人学校高等部卒業者は日本国内の大学の入学資格を得られる。
世界50か国・1地域に95校あり、約1万7千人が在籍(2020年4月現在)。
- 日本語補習校(日本語補習授業校)
-
平日(月~金)は現地校やインターナショナルスクールなどに通っている子供に対し、土曜日や平日の放課後などに、日本政府の定める教育課程に沿った授業を日本語で行う教育施設。海外在住の児童生徒が将来日本の小学校または中学校の授業に十分適応できうるだけの学力養成を目的としている。
現地の日本人会や商工会が設立・運営母体となっている補習校が多い。通常、日本政府からの財政援助がある。
以前は駐在家庭の子女が多かったが、現在では永住家庭(国際結婚家庭)の子が増えている。日本人学校がない地域では、駐在員子女も通っている。
世界55か国・1地域に229校あり、約2万2千人が在籍(2020年4月現在)。
- 継承語としての日本語教育機関
-
「継承語」としての日本語教育を通して、海外に在住する子供達に日本人としてのアイデンティティーを残すことを目的に、有志によって設立された日本語教育施設。
授業は、土曜日や平日の放課後。ほとんどが永住家庭(国際結婚家庭)の子。
「継承語」とは?
「継承語」とは、親から受け継いだ、家庭で話す言語のこと。
「継承語」に対して、子供が育つ環境(学校、家庭外)で日常的に使う言語のことを「現地語」と呼びます。
住んでいる地域に補習校があるかどうか調べる方法
日本語補習校のリストは、お住まいの地域を管轄する日本国大使館・総領事館のホームページに掲載されていることが多いです。
大使館・総領事館の「子女教育」「教育情報」「教育機関」「教育施設」といったページに掲載されています(領事情報の中に入っていることもあります)。
例えば、ニューヨークのような大都市だと色々な学校がありますが、まず在ニューヨーク日本国総領事館の日本語補習授業校一覧を確認すると一覧が確認できます。
補習校には、何歳から何歳まで通えるの?
補習校に何歳から何歳まで通えるかは、補習校によってまちまちです。
通常、どこの補習校にも小学部と中学部があります。
学年が上がるにつれ辞める子が多く人数がどんどん減っていくので、規模が小さな補習校では上の学年が複式学級になることも。
補習校によっては、幼稚部や高等部があったり、ベルリン日本語授業補習校のように0歳児から通えるクラスを備えたところもあります。
補習校の1年間のスケジュールは? 補習校の新学期は何月?


日本の学校と同じように、補習校は、新学期が4月に始まる3学期制です。
4月に始業式/入学式があり、3月(または2月)に終業式/卒業式があります。
大体、どこの補習校にも、夏休み、冬休み、春休みがあります。現地校が夏休みに入る頃に補習校も夏休みに入り、現地校の新学期が始まる頃に補習校の2学期が始まります。
1年の授業回数は補習校によってばらつきがありますが、週1回開校で、1年間に33回~44回程度です。
補習校の時間割は?
補習校には、半日授業を行う学校と1日授業を行う学校があります。
半日制の学校の授業は、平日午後または土曜日の午前または午後に設定されているところが多いです。



1コマ40分~50分の授業を、休憩を挟みながら3コマ行う補習校が多数派です。
1日授業を行う学校は、通常土曜日に授業を行っています。
土曜日は、「音楽やスポーツなどの習い事を優先したい」「家族で過ごす時間を大切にしたい」「旅行したい」という理由で補習校に行かない人もいます。
補習校が平日夜に設定されている方が、週末の時間を有意義に使えて保護者の評判が良いようです。
「子供を補習校には行かせたいけど、土曜日は空けておきたい」という方には、オンラインの日本語補習校の授業を受けるという選択肢もありますよ!
うちの子たちが通っていたカナダの補習校は、土曜日の9:00~15:30、1コマ50分の授業が6コマみっちりありました。お弁当が必要で、補習校に通うことで土曜日が丸一日潰れる感じでした。
ドイツの補習校は、土曜日の午前または午後に1コマ45分の授業が3コマありました。
補習校で学べる教科は? 使用する教科書や教材は?


補習校では国語を中心に学ぶ
補習校では国語を中心に学びます。
補習校によっては、国語以外に、算数/数学、理科、社会(歴史・地理)が学べるところもあります(国語以外の教科が選択制になっているところもあります)。



カナダの補習校(1日6コマ)は、国語が3コマ、算数/数学が2コマ、社会または理科が1コマという感じでした。
ドイツの補習校(半日制)では、小学生クラスは国語(読解)・国語(漢字)・算数が各1コマ、中学生クラスは国語が3コマでした。
国語の授業では
物語文や説明文を学ぶだけではなく、学齢に応じて、様々な詩、俳句、短歌などを学び、落語(小5)や狂言(小6)などにも触れます。
次男は落語がとても気に入って、「寿限無(じゅげむ)」や「初天神」の動画を何度も何度も見ていました(もちろん語彙や言い回しが難しいので全部はわかっていませんが)。
また、うちの子たちは、国語の授業を通じて、第二次世界大戦下での人々の生活や空襲、原爆について知り、興味を持つきっかけになりました。
家庭だけで日本語学習をしていると、こういった日本の伝統芸能や歴史に触れる機会ってあまりないですし、教えにくいので、補習校で少しでも教えてもらえるのはありがたいです。
また、学齢に応じて、観察日記や作文の書き方、話し言葉と書き言葉の違い、敬語の種類と使い方などを学べるのも補習校で国語を学ぶことの大きなメリットだと思います。
「書く」ことを家庭で教えるのって難しいですよね。
補習校では、「はじめ」「中」「終わり」の構成を学び、実際に書く作業を繰り返すことで、だんだんと日本語を「書く」能力が身についていきます。
意外!? 補習校で日本の算数を学ぶことをおすすめする理由
補習校で算数を学ぶことについて、最初は「算数は世界共通だし、補習校で学ばなくてもいいのに。それより国語をしっかりやってほしいなぁ。」と思っていました。
ですが、実際補習校で子供たちが算数を習い始めて「補習校で算数が学べてよかった!」と心から思うようになりました。



補習校の保護者の中には「日本の算数を学ばせるために補習校に入れた。」という人もいたんですよ。
例えば、補習校の小2の算数では、日本ならではの九九を習いますが、補習校で日本の九九をマスターしたことで、その後子供たちは現地校の算数でとても楽をしました。日本の九九の覚え方って素晴らしいですね。子供たちは、九九は今でも頭の中で日本語だそうです。
実は、カナダやフランスの学校(現地校)では、小学校高学年になっても九九ができなかったり、時間がかかったりする子が結構います。うちの子たちは、現地校で九九のスピードテスト(例えば50問の九九を何分で解けるかというようなテスト)があったら、いつもクラスで1番か2番だったようです(大体カナダの学校でのトップグループは、公文で鍛えている中国人か、日本式の九九をマスターしている日本人)。



カナダの補習校の先生は、普通の九九だけでなく「下がり九九」「一つ飛ばし九九」などもやり、しっかり九九ができるよう数週間かけて鍛えてくださいました!
算数は、単純な計算問題以外は、日本語の文章読解力がないと解けませんよね。
また、小学生で習う算数用語って私たちが思っている以上にたくさんあるんですよね。「時刻」と「時間」の違い、億、兆、偶数、奇数、半径、直径、円周率、小数、整数、最小公倍数、最大公約数、上から2けたのがい数、対角線、垂直、平行、二等辺三角形、通分、約分、帯分数など...他にもまだまだたくさんあります。
補習校で算数を勉強していたおかげで日本の小学校で体験入学した時も、漢字はともかく、算数の授業はまったく問題なくついていけました。
ちなみに、カナダ/フランスと日本では、数字の「2」と「7」の書き方が違ったり、筆算の書き方が違ったりしますが、うちの子たちは書き方を器用に使い分けていました。
補習校で使用する教科書や教材
補習校で使用する教科書
補習校の小中学生は、日本政府から無償で配布される教科書を使って授業を受けます。
(日本国籍をお持ちでないお子さんは無償配布の対象にならないため、別途購入する必要があります。)
日本在住で、海外に到着後すぐに補習校に通われる場合は、日本から出国する前に補習校で使用する教科書を入手しておく必要があります。海外子女教育振興財団で入手できます。
海外にお住まいの場合は、お住まいの地域を管轄する大使館・総領事館を通じて入手します。
海外にお住まいの場合の教科書入手方法はこちら
補習校の幼児部に通っていない(幼児部がない)場合、補習校の小学1年生で使用する教科書は、大使館・総領事館を通じて、幼稚園の年長の9月(補習校に入学する半年前)に申し込んでおかないといけないので注意が必要です。
通常、補習校入学後は、補習校が在校生分の教科書の申込・受領をまとめて行うので、個人で大使館・総領事館を通じて申し込む必要はありません(入学後、念のため確認してください)。
使用する教科書の種類は補習校によって異なります。
ご参考までに、うちの子たちが補習校で使用していた教科書は次の通り。
- カナダの補習校(1日)・・・「国語」「算数」「社会」「理科」、小1・小2は「生活」、たまに「道徳」(音読の宿題)。中学生は「地理」「歴史」も使用。
- ドイツの補習校(半日)・・・「国語」「算数」。社会(選択制)をやっている人は「社会」
補習校で使用する教材
教材(主に家庭学習用)として、国語ドリル、算数ドリル、漢字ドリルなどを使用します(補習校が日本から取り寄せます)。
また、各担任の先生が、授業中に使うプリント、宿題用のプリントを用意します。
補習校に通えば漢字が身につくの?


永住家庭(国際結婚家庭)のお子さんは、日本の子に比べると圧倒的に日本語で読み書きする時間が少なく、家庭外で漢字が目に入る機会も少なく、漢字だけでなくその言葉の意味自体知らないことも多いので、漢字の習得には苦労します。
小学校低学年では、子供たちがすでに意味を知っている言葉の漢字(しかも、訓読みだけ)を習います。
どこの補習校でも低学年の頃は比較的漢字学習に時間を取ってくれるので、国際結婚家庭のお子さんは大体小学3年生ぐらいまでの漢字はなんとか覚えられているように思います。
小学校高学年になると、すでに訓読みを習った(読み方はひとつだけだと思っていた)漢字の音読みがしらっと登場したり、新出漢字を習う時に音読みと訓読みの両方をいっぺんに覚えないといけなくなったりして、混乱し始めます。
小学5~6年生になると、専門的な分野で使われる言葉(日本のお子さんなら意味は知っているであろう言葉)の漢字が登場します。国際結婚家庭のお子さんは、まず言葉の意味を覚え、漢字の音読み・訓読みも覚えないといけないので、さらにハードルがあがります。
補習校ではほぼ毎回新出漢字の漢字テストがあります。
ただ、一度覚えて漢字テストをやっただけでは身に付かないんですよね。習った漢字を定期的に復習したり、家庭で色々な読み物の音読をして既出漢字に触れる機会を増やしたりして、繰り返し繰り返し覚えていくしかありません。
補習校によっては、補習校で漢字検定試験を受けられるところもあるので、挑戦してみるのもいいかもしれませんね。
補習校の宿題量は? 現地校と両立するのは大変?


補習校では家庭でのサポートが不可欠
補習校の目的は「将来日本に帰国した時に小・中学校の授業に十分適応できるようにすること」なので、日本の子供たちが月~金曜日の5日間で学ぶことを補習校の子供たちはたった1日(半日)で学ばないといけません。
もちろん1日(半日)で学ぶなんて無理なので、家庭での保護者のサポートが不可欠です。
補習校では、家庭できちんとサポートしている前提で授業を進めていきます。
体験談その1: カナダの補習校の宿題はこんな感じでした
うちの子たちがカナダで通っていた補習校では、月曜日から金曜日の夜毎日少しずつやらないと終わらないほどたくさん宿題が出されていました。
土曜日の補習校が終わったら、週末に宿題の内容と量を確認。
月曜日から金曜日にかけて少しずつ計画的に宿題をやる。基本的に、音読は毎日。
金曜日の夜、翌日の漢字テストのために漢字の復習をする。



こんな感じで、平日の月曜日から金曜日の夜は、土曜日の補習校のために存在しているような感じでした...
学年が上がって宿題が多くなると、1日2時間以上やっていた時もあったと思います。
「補習校の宿題は大変」ってよく言われることですが、確かに我が家は大変でした(宿題をやる子供も、それをみる私も)。
でも、日本語力が足りない永住家庭(国際結婚家庭)のお子さんにとって大変なのであって、駐在員家庭のお子さんたちは、親御さんの手を煩わせることなく涼しい顔をしてやっていました。
毎週出される宿題が、音読と漢字ドリル(漢字テストに向けた勉強)。
あとは、国語は、読解問題(ドリルやプリント)、新出語彙の意味調べ/短文作り、詩や俳句の暗唱、作文、クラス発表の準備など、算数は練習問題(ドリルやプリント)といった宿題が出ます。
夏休みや冬休みなどの長期の休みもしっかり宿題が出ます。夏休みは、大量の国語・算数プリントに加え、あさがお(小1)やプチトマト(小2)の観察日記、日記、読書感想文、漢字50問テストの勉強など。冬休みは文集の下書きなど。日本の全都道府県名の漢字テストに向けた勉強、っていうのもありました。
カナダの補習校では、
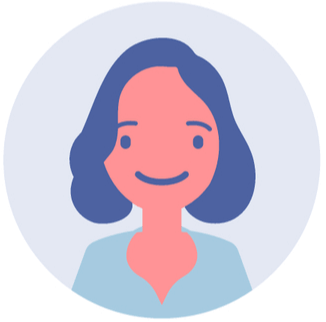
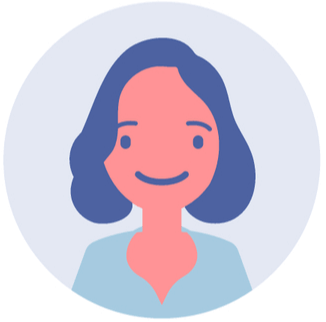
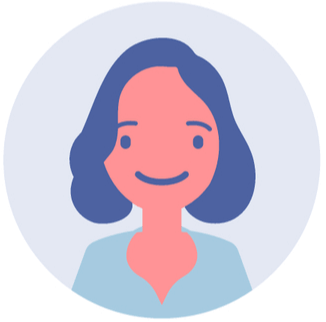
子供がなかなか宿題をやらないから、喧嘩になってランドセルをゴミ箱に捨てちゃった。(あとで拾ったけどね。)



金曜日の夜10時になっても宿題終わってないから叱って泣かせた...
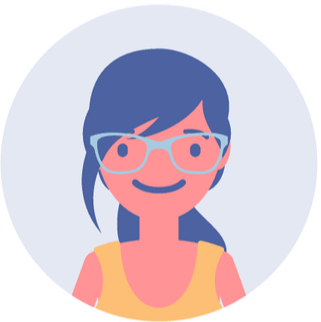
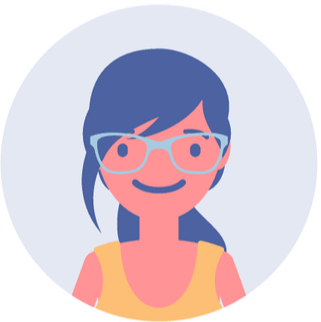
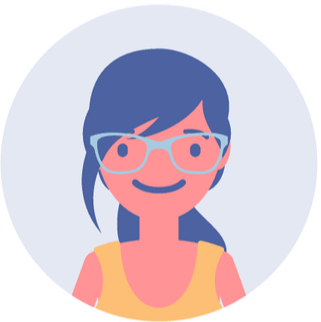
あまりの宿題の多さに、夫(外国人)が「そんなにたくさん宿題やらせなくてもいいだろ!」って怒って、宿題隠しちゃったのよ~
そんなエピソードには事欠きませんでした(笑)。
現地校も学年が上がるにつれ宿題が増えてきて、現地校と補習校の両立が大変になっていきます。
子供が補習校が嫌になる一番の理由はやっぱり宿題の多さだと思います。「補習校は楽しいけど宿題は嫌。」という子が結構います。
我が家の長男も次男も補習校を辞めたい時期がありました。
小学生ぐらいだとまだここまでして日本語を学ぶ意味がわかりません。「日本のおじいちゃんおばあちゃんやいとこと話せなくなるよ。」「日本語ができたら日本の体験入学が楽しくなるよ。」と言うと頷くけれど、やっぱり親にやらされている感がありますよね。
長男には「せっかくここまで頑張ってきたんだし、皆頑張ってるし、とりあえず卒業式までがんばろう!」と言って、一緒に頑張りました(長男自身も卒業証書はもらいたかったみたいですし)。
【長男のその後】
長男は、カナダからドイツに引っ越す時に「もう補習校には行かない」と決めてしばらく休んでいました。
ですが、次男が楽しそうにドイツの補習校に通っている様子を見て、自分から補習校に行きたいと言い出しました(びっくり)。
ちょうど年齢的(13歳)にも、自分が日本人であることを再認識し(現地校で先生や友達に日本のことを聞かれたりする機会が増えた)、日本語を勉強する意義が自分なりに分かってきたみたいです。



13~14歳頃から日本人としての自己認識が現れ、日本語を学ぶ意義を考えたり、分かり始めたりするようになるのは、我が家に限ったことではないようです。他の保護者の方も言っていました。
なので、しんどいですが、頑張れるならそのぐらいの年齢まで頑張ってみるのもよいかも、です。
体験談その2: ドイツの補習校の宿題はこんな感じでした
カナダの補習校しか知らなかった時は、どこの補習校でも宿題は多いのだろうと思っていました。
ドイツの補習校に子供を通わせてみて、宿題量も補習校によって違うことがわかりました。
ドイツの補習校では、小学生の宿題の基本はやはり音読と漢字ですが、音読を除けば、金曜日の夜やれば終わるぐらいの宿題量です。
長男(中学生)の宿題量も多くありません。これなら、宿題が多い現地校との両立も可能で、長く続けられます。



最近は、どうやったら子供たちが長く楽しく日本語の勉強を続けていけるかが重要だと思っています。
補習校にはどんな子が通っているの?


駐在家庭の子供と永住家庭の子供の比率
もともと補習校は、日本人学校がない都市で、日本人会や商工会が設立した学校である場合が多いです。
なので、一昔前は、駐在家庭の子女にしか門戸を開いていない補習校もありました。うちの子たちが通っていたカナダの補習校も、昔は永住家庭(国際結婚家庭)の子女は受け入れておらず、当時補習校に通いたくても通えなかった国際結婚家庭のお子さん(と言っても今は大人ですが)に「いいですね、今はハーフの子も受け入れてもらえて...羨ましい。」と言われたことがあります。
今は、昔に比べて海外赴任自体減っているので、どこの補習校も永住家庭の子を受け入れないと運営が成り立たなくなりました。補習校の運営は児童生徒数にかかっていますからね。



実際、うちの子たちが通っていたカナダの補習校も、ドイツの補習校も、ほとんどが永住家庭のお子さんでした。
カナダで住んでいた都市には日本人学校がなかったので、駐在家庭、長期滞在の邦人家庭(大学の研究者など)には子供を日本人学校に通わせるという選択肢はなく、そのため、補習校の駐在家庭、長期滞在の邦人家庭の比率は比較的高めでした。両親ともが日本人というご家庭のお子さんは2割ぐらいだったと思います。
その後ドイツで住んだ都市には日本人学校があったので、補習校に通う、駐在家庭、長期滞在の邦人家庭のお子さんはかなり少なかったです。次男(小学校高学年)のクラスは100%永住家庭のお子さんでした。
ニューヨークやロンドンのような大都市だと、駐在家庭/長期滞在の邦人家庭であっても、お子さんが英語を身につけるため平日は現地校やインターナショナルスクールに通い、土曜日は補習校に通うというパターンも多いと思います。
ですが、小さな都市で日本からの駐在員が来ないような場所の補習校だと、永住家庭のお子さんしかいないということも珍しくありません。
駐在家庭の子供と永住家庭の子供がいっしょに勉強するのは難しい?
日本語レベルも学ぶ目的も違う
補習校で、駐在家庭のお子さんと永住家庭(国際結婚家庭)のお子さんがいっしょに勉強することは難しいです。
日本語レベルも、勉強する目的も異なるからです。
駐在家庭のお子さん
- 日本語は母語
- 日本帰国後に日本での学習に支障が出ないように学力を維持したい(帰国後、中学受験を控えているというお子さんも珍しくない)
永住家庭(国際結婚家庭)のお子さん
- 日本語は継承語
- 日本語力を身につけたい(維持したい)。日本の行事や学校文化を体験したい。
各補習校が、永住家庭のお子さんにどの程度配慮し、授業を行っているかにもよりますが、
駐在家庭の保護者からは、
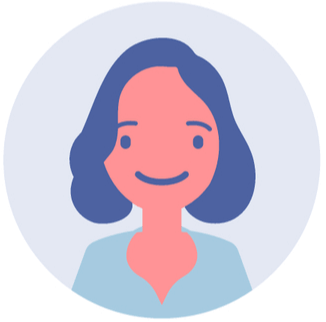
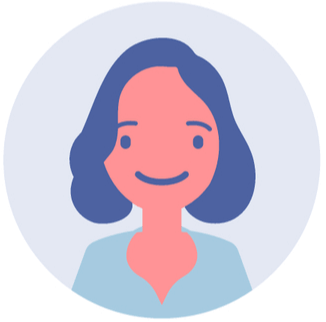
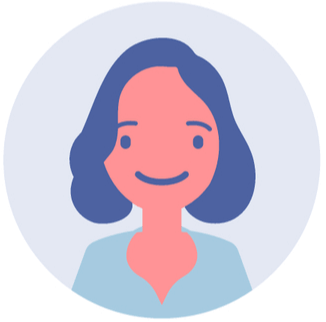
もっと授業の難易度、進度を上げてほしい!
永住家庭の保護者からは、
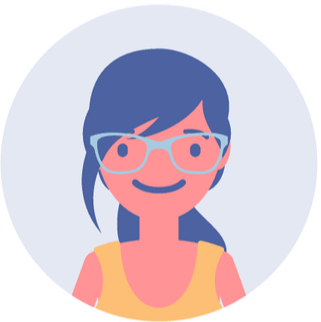
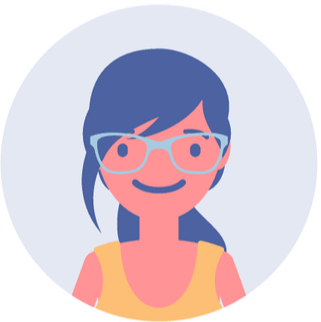
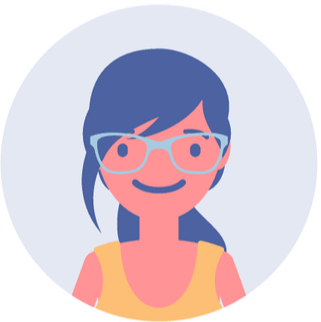
補習校に通っているほとんどが永住家庭の子なんだから、配慮してほしい!
という声があります。
補習校によって、授業内容/日本語レベル/保護者の期待は様々
同じように日本政府から財政援助を受けている補習校でも、
- 補習校の運営母体(日本人会?商工会?永住家庭の保護者有志?)
- 駐在家庭、長期滞在の邦人家庭、永住家庭のお子さんの割合
- 授業時間数
などによって、補習校の授業内容や、通っているお子さんの日本語レベル、保護者が補習校に期待することなどが違います。
うちの子たちが通っていたカナダの補習校は、もともと商工会が設立した補習校です(運営役員にも商工会メンバーが入っていて、毎年商工会からの寄付があります)。補習校の意義については、入学時だけでなく、毎年保護者総会で保護者全員にリマインドされます。なので、永住家庭のお子さんの方が多いのにもかかわらず、「永住家庭の子に配慮した授業を行ってほしい」「継承語としての日本語教育を行ってほしい」という保護者はいませんでした。(そんなこと言ったら、「じゃあ、継承語としての日本語教育を行う教育機関に行ってください」「家庭教師をつけたらどうですか」などと言われてしまうでしょう...)
一方、ドイツの補習校では、「何よりも楽しく学べることが大切」「日本の行事や文化を学んでほしい」という考えの保護者が多かったです。また、全員が永住家庭のお子さんである次男のクラスでは永住家庭のお子さんに配慮した授業内容になっていました。
カナダの補習校では、小学校低学年の時を除いて、漢字は主に家庭学習で習得すべきものとされていて、国語の授業では、読解や作文、皆の前での発表などが主でした。
一方、ドイツの補習校では、小学校高学年でも、国語の時間の半分が漢字の時間で、クラス内でいっしょに漢字を書いたり、その漢字を使った例文を作ったりと、漢字学習に力を入れていました(つまり、永住家庭のお子さんに配慮した授業内容)。
ハーフの子を持つ親として、2つの異なるタイプの補習校を経験しましたが、正直どちらのタイプの補習校がよいのか一概には言えないと思っています。それぞれにメリット、デメリットがあるからです。
カナダの補習校の方がドイツの補習校より小学校6年間で計700時間近く授業時間が多く、国語の教科書はほぼ終えられます。宿題が多いので、家庭でのサポートをしっかりしていないと、国際結婚家庭のお子さんは補習校の授業についていけなくなります。常に宿題に追われる生活で、親も子もストレスがたまります(うちの子も何度か「補習校を辞めたい」と言いました)。中学生になると、補習校と現地校の両立が大変になり、やめていくお子さんがいます。ただ、頑張った分だけ結果がついてきます。子供の日本語力は高くなり、日本の小学校に体験入学しても問題なく授業についていけます。
一方、ドイツの補習校では、国語の教科書を主に授業を進めますが、すべての単元はやりません(永住家庭の子に配慮した授業内容となっています)。宿題が少ないので、補習校で出された宿題だけをやっていたのでは、カナダの補習校ほど日本語力はつきません(それでも、国際結婚家庭で、日本語力がかなり高いお子さんもおられます。おそらく家庭で親御さんがすごく頑張っておられるのだと思います)。適度に家庭でサポートしていれば、無理なく授業についていけます。中学生になって現地校の勉強が大変になっても続けられます。つまり、長く楽しく日本語学習を続けられるというメリットがあります。
「補習校の授業レベルが低いので、子供を行かせるべきかどうか」迷っておられる駐在家庭の保護者の方へ
補習校で学べるのは国語(や算数/数学)だけではありません。
日本の様々な行事や学校文化を体験できたり、人の意見を聞いたり人前で発表したり、グループ活動の機会が持てたりします。日本語を話すお友達もできます。
特に、日本から来ていきなり現地校やインターナショナルスクールに入った場合、苦労している子が多いですが、「補習校に来ると自分の居場所ができたみたいでほっとする」という声を何度か聞きました(特に、小学校高学年~中学生のお子さん)。
とりあえず通ってみてお子さんの様子を見られてもいいかもしれませんね。
補習校の先生は教員免許を持っているの? どんな人が教えているの?


規模の大きい補習校では、日本の文部科学省から校長先生や教頭先生が派遣されているところがあります(例:ロンドン補習授業校、ニューヨーク補習授業校、シンガポール日本語授業補習校)。
一般の先生は、ほぼ現地採用。採用条件としては、教員免許保持は必須ではありません(教員免許必須にしたら、特に日本人がそれほど多くない地域では、教員が確保できなくなってしまいます)。
留学生が先生をしている場合もありますし、自分の子供を補習校に通わせながら自分は補習校の先生をしている、という人も結構います。



我が家は、長男・次男合わせて、これまで補習校2校で13人の先生にお世話になりました。
もう20年以上補習校で教えていてそれでも努力を怠らず毎年教え方がパワーアップしているベテラン先生。日本の教員免許を持っていて子供たちのメンタルな部分にも配慮できる先生。ご自身のお子さんの日本語学習も頑張っていて、国際結婚家庭のお子さんの間違いやすいところや苦手なところをよく分かっておられる先生。まだ若く生徒にとってはお兄さんのような先生...色々な先生がおられました。
補習校にお子さんを通わせている保護者は、どちらかといえば教育熱心です。保護者の補習校に対する期待値は高く、先生に対する評価も厳しくなりがちで、そのため補習校で教えることに苦労しておられる先生もおられました。
海外在住の国際結婚家庭のお子さんにとって、親以外の日本人の大人の話を聞く機会ってなかなかないと思います。そういった意味でも、多様な経歴やバックグラウンドをもつ日本人の先生に教えていただけるのは貴重なことだと思います。
補習校ではどんな行事や学校文化があるの?


補習校の行事
日本の学校のように、4月に始業式と入学式があり、3月(補習校によっては2月)に終業式と卒業式があります。毎回校長先生のお話があって、子供たちには退屈みたいですが、これも日本らしい良い経験です。
日本の学校のように、授業参観や保護者の懇談会、個人面談もあります。
補習校での行事のハイライトはなんと言っても運動会。うちの子たちも毎年喜んで参加していました。
徒競走、玉入れ、障害物競争(パン食い競争)、綱引き、借り物競争、親子で二人三脚など、補習校に通っていなかったら体験できなかっただろう運動会競技の数々。お昼は、芝生の上にレジャーシートを敷いて、家族やお友達と弁当を囲みます。最終競技の全学年紅白対抗リレーまで勝負がつかないことも多く、手に汗握ります。
入学したばかりのお子さんはリレーでのバトンの渡し方も知らないので、運動会前にバトン受け渡しの練習をしたり、息子と公園で二人三脚の練習をしたり(きっと外国人には変わったことをしていると思われているでしょう)、とても良い想い出です。
他にも、補習校によって異なりますが、様々な行事があります。
- 餅つき
- 書道
- こどもの日
- 七夕
- お月見
- 節分
- バザー(収益は日本語図書の購入などにあてられる)
こういった日本ならではの行事を体験できることも補習校の大きなメリットです。
補習校の学校文化
補習校によっては、日本の学校のように、授業開始・終了時の挨拶や、日直などがあります。
カナダの補習校は校舎として現地校校舎を借りていたので、きれいに掃除してお返ししないといけませんでしたが、昼食後のカフェテリアのテーブル拭き、教室の掃き掃除、トイレ掃除などは、子供たちが当番制でやっていました。
日本では、給食は教室で担任の先生といっしょに食べますが、カナダの補習校でも、担任の先生が子供たちの中に入ってお弁当を食べられていたのが印象的でした(現地校では、昼食時は先生は自由、子供たちとはいっしょに食べません)。
補習校では、日本の本も借りられる!
もし補習校が日本人学校の校舎を借りて授業を行っている場合、日本人学校の図書館を利用することができます。
カナダの補習校は現地校校舎を借りていましたが、充実した図書コーナーがあり、日本の本や漫画を借りることができました。
海外にいながら日本の本を借りることができるというのも、補習校のメリットです。
補習校の保護者は役員やボランティアが必須? 人間関係が煩わしい?
補習校の運営は、保護者の協力なくてはやっていけません。
子供たちが喜ぶ運動会などの行事はすべて、事前準備から当日の進行まで、保護者が行います。運動会以外にも、バザーを準備したり、貸出図書の管理をしたりするのも保護者の仕事です。
毎年各クラスでは保護者1名が「クラス委員」となり、補習校からの伝達事項を伝えたり、保護者の意見をとりまとめたり、補習校を辞めるお子さんがいると送別のメッセージを取りまとめたり送別のプレゼントを手配したりします。
カナダの補習校は現地校の校舎を借りて授業を行っていたので、小学校低学年の保護者は、授業終了後、当番制で、教室の掃除、整理整頓をする必要がありました。
もちろんすべてボランティアです。
子供が長く補習校に在籍していると、一度は役員やなんらかの委員をやらなければいけない、という空気になります。
補習校の日に仕事をしている方や、まだ小さなお子さんがいる方は、委員や係決めの時に配慮してもらえることがありますが、それでも大変だなと思う場合があります。
「役員やクラス委員決めがストレス。」「人間関係が煩わしい。」そのように思っている人もいると思います。



私は個人的に、補習校で他の保護者に出会えたことのメリットの方が大きいです。
現地情報を入手できたり、子供の日本語教育について相談できたり。皆でワイワイやりながら行事の準備をするのも楽しかったです。補習校以外で数家族で集まって遊ぶこともありました。
補習校の授業料は? 授業料以外に必要な費用は?


補習校の授業料
補習校によって、授業料は結構違います。
例えば、2023年度の小学1年生の授業料を比べてみると、1年間の授業料が約18万円(=1210 USドル、オハイオ州コロンバス日本語補習校)だったり、1年間の授業料が約35万5千円(=2373 USドル。ニューヨーク補習授業校)だったり。
補習校が半日授業だから安い、1日授業だから高いということではないようです。



現に、米国では授業料が安めのコロンバス日本語補習校は、1年に44回(補習校で最多)、1日授業を行っている学校です。
ちなみに、日本政府は、補習校に対して次のような財政援助を行っています。
- 校舎借料の一部
- 現地採用教員(講師)の給料の一部
- 現地採用講師研修会開催経費の一部
- 安全対策費の一部
各補習校に対する日本政府からの補助金の割合はそれほど変わらないと思うので、補習校による授業料の差は、もともとの校舎借料、日本人会や商工会などからの寄付額(そもそも寄付があるかどうか?)、児童生徒の在籍人数などによって変わってくるのかなと思います。
補習校の校舎は、現地の学校施設を借りたり、日本人学校の施設を借りたりするところが多いようです。
地元の教会の厚意でほぼ無料で教会施設を使わせてもらっているというような補習校もあり、そういった補習校では授業料を安く押さえることができますね。
ちなみに、補習校に兄弟で通う場合、2人目または3人目から授業料が割引になる学校があります。
補習校で必要となる、授業料以外の費用
補習校では、授業料以外の費用として、入学時に入学金が必要です。
入学金の額も補習校によってまちまちで、2023年度の入学金を比べてみると、安いところで約8,900円(=60 USドル。オハイオ州コロンバス日本語補習校)、高いところで約67,000円(=450 USドル。ニューヨーク補習授業校)です。
また、補習校によって、教材費、保護者会費、スクールバス代、管理費/セキュリティ費などが必要になる場合があります。
(各補習校の授業料及び経費は各補習校のホームページに明記されているので確認してみてください)。
夏休みにキャンプなどが予定されていれば、キャンプ参加費も必要となります(キャンプは自由参加)。
補習校を辞めるお子さんがいれば送別プレゼント代、学年末にはお世話になった先生へのプレゼント代(いずれも各家庭数百円程度の僅かな金額)をクラス委員さんが徴収するのが普通です。
補習校には日本国籍がなくても通えるの?
日本国籍がなくても通える補習校と、日本国籍保持を受け入れの条件としている補習校(例:シンガポール日本語補習授業校)があります。
日本国籍がなくても受け入れてもらえる補習校でも、学齢相応の日本語力がなければ受け入れてもらえません。
また、日本国籍がない場合、日本政府の教科書無償配布の対象とならないので、自費で教科書を入手する必要があります。
入学・編入時に試験や面接はあるの?
補習校では、日本の学習指導要領に合わせて「国語」を学ぶので、学齢相応の日本語力がないと授業についていけません。
小学校入学時点でひらがなをマスターしている必要はありません。



ただ、ある程度日本語ができていて、机に座って勉強するという習慣がついてないと、補習校に入ってから辛いと思います。
定員枠を設けている補習校も多いですし、小学校入学前には、入学説明会、面接試験があるところがあります。
補習校の1クラスあたりの人数はどれくらい?
1クラスの人数は、補習校によりまちまちです。
多いところでは、ニューヨーク補習授業校のように1クラスあたりの定員が25名というところがあります。
マンモス校では、1学年に複数のクラスがあります。
うちの子供たちが通っていたカナダの補習校の定員は1クラス17~18名でした。
ただ、学年が上がっていくにつれ辞める子が増えるので、1クラスあたりの人数が少なくなっていく傾向にあります。
長男も次男も、カナダの補習校入学前に面接試験がありました。
日本語で聞かれたことにきちんと答えられるか、という簡単なものでした。
「好きな食べ物は?」
「「強い」の反対は?」
「きゅうりは「野菜」。じゃあ、りんごは?」
「笛は「ふく」。じゃあ、太鼓は?」
「お母さんはどんな人?」
というような質問がありました。



どうしても補習校に子供を入れたくて、面接試験対策で、母子2人日本に数週間一時帰国して面接試験に備えたっていう保護者もいました!
ドイツの補習校に編入する際は、定員にも空きがあったのか、特に試験などはありませんでした(カナダで補習校に通っていたことは伝えました)。
補習校に通うために各自準備しなければならないものは?


補習校によって用意しなければならないものは異なります(各補習校のホームページで、または、直接問い合わせてご確認ください)。
ご参考までに、うちの子たちが補習校に通うために用意したもののリストです。
- ランドセル(普通のリュックでOK。我が家は日本のいとこから譲り受けたものを持ってきました。カナダの補習校では3割ぐらいの小学生のお子さんがランドセルを使っていたように思います)
- 筆箱(現地校で使っているものでよい)
- 鉛筆(うちの子は入学時は2B、現在はBを使っています。今どきの子は筆圧が弱く、日本の小学生が使用している鉛筆の主流は2Bだそうです)
- 赤鉛筆(補習校で購入可。色鉛筆の赤ではなくて、丸つけ用の赤鉛筆が必要と言われたので用意したのですが、正直色鉛筆セットの赤でいいのでは、と今でも思っています)
- 筆箱に入れられる鉛筆削り
- 消しゴム
- 定規
- 下敷き(外国では使わない?)
- クリアファイルや紙フォルダー数枚(宿題を入れて提出したり、配布プリントを綴じたりするため)
- 日本の学習ノート(カナダの補習校では、学年によってマス数や行数が細かく指定されていました。補習校で購入可)
- 算数の授業で、30cmの竹の定規(補習校で購入可)、コンパス、三角定規、分度器
- 小学生用の国語辞典(小学3年生の授業で国語辞典の使い方を習います。我が家では、国語の教科書の出版社「光村図書」が出版している国語辞典を使用)
- 漢字辞典(小学4年生の授業で漢字辞典の使い方を習います)
- 紅白帽(運動会の時に使用。日本の100円ショップのものでOK)
補習校から貸してもらえるため、必要なかったものは次の2つ。
- 習字道具
- そろばん
習字道具やリコーダーも各自準備しないといけない補習校もあるようです(例:コロンバス日本語補習校)。
これは別に補習校で使う文房具に限った話ではないですが...日本の文房具は質がよくて安いので、鉛筆、赤鉛筆、消しゴム、鉛筆削り、下敷き、クリアファイル、定規、コンパス、三角定規、分度器などは、一時帰国時に用意されることをおすすめします。(日本の学習ノートも補習校で買うより日本で買った方が安いですが、マス数や行数がはっきり分かってないと買えないんですよね。)



カナダの鉛筆削りはフタがすぐ取れるし、よく削れない。
定規類はメモリの線がすぐに消える(定規の意味ない)。
コンパスは、現地校でも必要なので何種類も買いましたが、子供たちによると日本のコンパスが一番使いやすいそうです。
うちの子たちは、漢字辞典はたまにしか使っていないんですが、国語辞典は小学校3~4年生頃からよく使っているので、お子さんが補習校に通われるなら早い段階で買っておかれることをおすすめします。
カナダの補習校で、小学2年生の3月になって「小学3年生の前期の授業で国語辞典が必要になるので用意してください」と突然言われ、急いで日本で買って実家の母にカナダまで送ってもらいました。もっと早くに知っていたら夏休みに一時帰国した時に買って持ってこれたのに...
小学生用の国語辞典は、海外在住のお子さんに無償で配布される国語の教科書の出版社(光村)が出しているものがおすすめです。同じ出版社が出しているものなので、国語の教科書に出てくる言葉はもちろんすべて載っていますし、他の出版社の国語辞典に比べると料金も良心的なので。(日本の小学校でも光村の国語辞典を指定、推薦するところも多いようですよ。)



うちの子たちが小学生用の国語辞典を使ったのは、小学3~4年生ぐらいから6年生まで。
中学生になったら、教科書に載っている言葉を調べても載っていないものが増えてきて、辞書を買い直す必要が出てきます。
日本語補習校のメリット・デメリットのまとめ
長くなりましたので、最後に、主に永住家庭(国際結婚家庭)のお子さんにとっての、補習校に通うことのメリットとデメリットをまとめておきます。
補習校に通うことのメリット
- 日本語力がつく(維持できる)。
- 国語の授業を通して、説明文や物語文だけでなく、学齢に応じて、詩、俳句、短歌、落語、狂言など幅広い内容に触れることができる。
- (算数を教える補習校の場合)日本の九九など日本の算数を学ぶことができ、現地校でも算数が得意になる。
- 運動会などの日本の行事や学校文化を体験できる。
- 同じように日本語学習を頑張っている友達ができる。日本語で遊ぶ友達ができる。
- 日本語の本や漫画を借りることができる。
- 日本一時帰国時の小学校での体験入学がより楽しくなる。
- 補習校によっては、漢字検定を受験できる。
- 海外在住の国際結婚家庭のお子さんにとっては、親以外の日本人の大人の話を聞いたり、会話したりする機会はあまりないが、補習校に通うことで、親以外の大人(先生、保護者)の話を聞いたり、会話をしたりする機会が持てる。
- 保護者も、他の日本人と知り合える。
補習校に通うことのデメリット
- 宿題が多い補習校では、現地校との両立が難しくなる可能性がある。
- 宿題が多い補習校では、親子間のけんかが増え、親も子もストレスを感じる(かもしれない)。
- 土曜日開校の補習校の場合、音楽やスポーツなどの習い事をあきらめないといけない場合がある。週末家族で過ごしたり、旅行をしたりする時間が減る。
- 補習校の先生になるには教員免許は必須ではない。未経験者、留学生も先生をしている場合があり、保護者の期待にそえない場合がある。
- 「永住家庭(国際結婚家庭)のお子さんばかり」という状況でない限り、永住家庭のお子さんに配慮した授業を行ってくれない。逆に、永住家庭(国際結婚家庭)のお子さんばかりだとどうしても永住家庭のお子さんに配慮した授業を行うことになってしまうので、駐在家庭(両親とも日本人)のお子さんには授業レベルが物足りない場合がある。
- 保護者は、役員やボランティアが必須。フルタイムで働いていたり、補習校の日に仕事が入ったり、小さなお子さんがいたりする保護者には困難な場合がある。
- 人によっては、人間関係が煩わしいと感じる。役員決め、クラス委員決めがストレスになる。
- 補習校によっては、授業料や入学金が高い。
我が家は、大変な時期もありましたが、息切れしそうになりながらもなんとかやってこれました。
海外で、家庭内に自分しか日本語を母語とする者がいない環境で、子供たちに日本語教育を行っていくというのは、本当に長く孤独な闘い(笑)だと思うので、補習校で他のママさん&パパさんや他のお子さんたちに出会えてよかったです。
補習校に行っていなかったら子供たちの日本語教育とっくの昔に挫折していたと思うので、私はやっぱり子供たちを補習校に行かせてよかったと思っています。
ある意味「強制力」「環境の力」があるから、ここまでやってこられたのだと思います。
もしお子さんを補習校に行かせようかどうしようか迷っておられるなら、とりあえず行かせてみて様子を見られてはいかがでしょうか。(海外在住の国際結婚家庭のお子さんが、家庭学習を頑張って、途中から補習校に編入するって結構大変です。補習校によっては、入りたい時にはもう空きがないってこともありますし。)
超長文記事、最後まで読んでくださってありがとうございました!
私は日仏ミックスの子2人の日本語学習について10年以上試行錯誤してきましたが、その中で実際に効果があった方法や教材などを、別記事でご紹介しています。