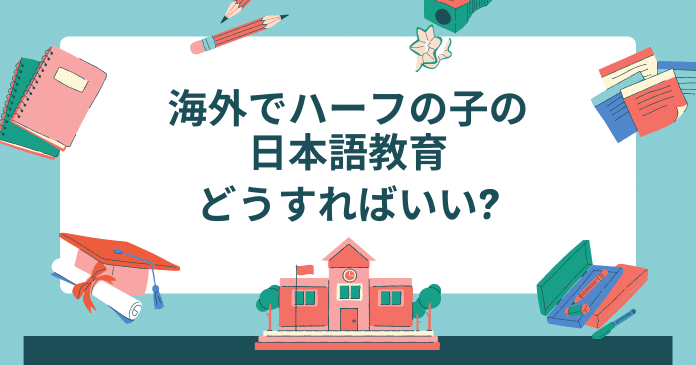こんにちは!フランス在住のKokoです。
我が家には、日仏家庭に生まれ一度も日本に住んだことがない子供が2人います(日本の学年だと、長男は高1、次男は中2)。
さて、国際結婚家庭のお子さんを持つ海外在住の皆さん、お子さんの日本語教育はどうしておられますか?
「これから日本語教育どうやっていこうかな?」「今のやり方でいいのかな?」と悩んでおられる方が多いのではないかと思います。
 Koko
Koko私自身、10年以上、子供たちへの「継承語としての日本語教育」をどのようにやっていったらいいのか、常に悩みながら、色々試行錯誤しながらやってきました。
この記事では、次のようなことについて書いています。
- 継承語としての日本語教育とは?継承語としての日本語教育の重要な鍵となるのは?気を付けるべきことは?
- 海外で日本語を学べる場所は?
- 海外で日本語を学べる教材や方法は?(うちの子たちに効果があったと思う教材や方法)
- 私がこれまで10年以上、子供たちの日本語教育についてどのように試行錯誤してきたか?
「国際結婚家庭のお子さん」と一言でいっても、お子さんを取り巻く言語環境は多種多様なわけですし、日本語教育をどうするか、各家庭で方針ややり方は様々だと思います。
ですので、ひとつのやり方として、参考にしていただけましたら幸いです!
継承語としての日本語教育とは?


「継承語」とは?
「継承語」という言葉をご存じですか?
私自身、子供たちの日本語教育に関心をもつようになるまで、「継承語」という言葉は知りませんでした。
元となる「heritage language」という言葉は、もともと1967年にカナダのオンタリオ州の「継承語プログラム」で初めて使用された言葉だそうです。
のちに、それが日本語に訳されて「継承語」に。
「継承語」とは何か?「現地語」「外国語」と比べるととわかりやすいです。
- 現地語・・・子供が育つ環境(学校、家庭外)で日常的に使う言語。
- 継承語・・・親から受け継いだ、家庭で話す言語。
- 外国語・・・文法や発音、言語の背景にある文化などについて、学校でゼロから学ぶ言語。
「継承語」はひとつであるとは限りません。アメリカやカナダのように移民が多い国では、「継承語」が2つ(父の母語と母の母語)あることは珍しいことではありません。
カナダにいる私の友人のお子さんは、現地語はフランス語(ケベック州公用語)、継承語は日本語(母の母語)とロシア語(父の母語)、両親のコミュニケーションは英語という言語環境にあり、彼女はこれからどうやってお子さんに継承語としての日本語教育、ロシア語教育をしていくべきか頭を悩ませています。



海外で生活しているお子さんの言語環境はまさに多種多様で、興味深いですね。
「継承語として日本語を学ぶ」とは?
「継承語として日本語を学ぶ」というのは、海外で生活する子供たちが、現地語とは別に、親の母語である日本語を習得するということです。
「継承語」として日本語を学ぶのと、「国語」という教科で日本語を学ぶのは違います。
「国語」という教科で日本語を学ぶというのは、小さい頃から、家庭、保育園/幼稚園/学校、社会などで、絶えず日本語にどっぷり漬かって日本語の基本的なことをすでに習得していることを前提に、読み書きや読解などを学ぶということです。
海外で生まれ育ったお子さんのほとんどは、小さい頃からそういった環境に身をおくことは難しく、日本の同年齢のお子さんだったら身についているような日本語の基本が身についていません。
なので、国際結婚家庭のお子さんが日本語補習校などで日本のレベルに合わせて「国語」の授業を受けるには、お子さん自身のかなりの努力、保護者の家庭でのサポートが必要になります。



うちの長男(中学生)が日本語補習校に通っていた時、両親とも日本人のお子さんたちの発言内容(語彙)が時々理解できないことがあったそうです。
日本で育ったお子さんたちに比べると、長男の日本語の語彙力は3年以上遅れていたんじゃないかと...
継承語として日本語を学ぶことの目的は?
海外で生活する子供たちが、継承語として日本語を学ぶ目的は、次のようなものです。
- 日本人の親や親族などとコミュニケーションを取る
- 「継承文化」としての日本文化を保持する
- 日本人としてのルーツに誇りをもつ
継承語として日本語を学ぶことで、「自分のルーツは?」「自分は何者なのか?」というアイデンティティ形成、人格形成に役立ちます。
【ご参考】日仏家庭の我が家の言語環境、日本語を学ぶ理由は?
日仏家庭の我が家の言語環境
日仏家庭のうちの子たち(中高生)の言語環境は次の通りです。
- 現地語・・・フランス語(在住国の言語。父の母語)
- 継承語・・・日本語(母の母語)
- 外国語1・・・ドイツ語(学校は仏独バイリンガル)
- 外国語2・・・英語



家族団らんの場ではどうしてもフランス語が優勢になってしまいがちです。
私が子供たちの日本語教育を頑張ろうと思った理由
私の義母はイタリア人で、私の夫はフランスで生まれ育ったのですが、義母は子供には常にフランス語だけで接してきました。
そして、夫はずっと、義母がイタリア語で話してくれなかったこと、イタリア語を教えてくれなかったことを悔やんでいました。自分のアイデンティティやルーツについて悩むということはなかったようですが、「もしイタリア語で話しかけてくれていたら、今こうしてイタリア語の本を買って苦労して勉強する必要はなかったのに」と。(←それでも、フランス語とイタリア語は近いので、私たちがイタリア語を勉強する時の苦労とは雲泥の差ですけどね。)
なので、夫にとって「自分たちの子供に日本語を教える」というのは疑う余地のないことでした(夫のこの強い思いは、継承語として日本語教育を続けていく上でとても助かっています)。
もちろん私や私の日本の家族と日本語でコミュニケーションできるようになるのは大切なことです。
また、私が気になったのが、国際結婚家庭のお子さんが思春期に自分のアイデンティティやルーツについて悩むことがよくある、と聞いたことでした。なので、日本語や日本文化を学ぶことで、日本人としてのルーツに誇りをもちアイデンティティ形成の助けになれば、という思いもありました。
継承語としての日本語教育の重要な鍵となるのは?
そして今、10年以上子供たちの日本語教育に向き合ってきて、継承語としての日本語教育にとって重要な鍵となるのは、次のようなことなんじゃないかと思っています。
- 子供たちを取り巻く人たち、特に、父親と母親が「継承語としての日本語教育」に対して同じ姿勢、熱意を持ち続けること
- 父親と母親がお互いの文化に興味をもち、リスペクトすること
- 父親と母親の間だけでなく、子供たちと日本語を学ぶ意義や目標について話し合い、子供たち自身が日本語を学ぶ意義を見い出すこと
まず、子供に日本語を継承語として教えていく上で、配偶者をはじめとしたまわりの家族の協力、理解は不可欠だと思います。
これまで、



外国人夫が理解してくれないから(協力してくれないから)、日本語補習校を辞めさせることにした。
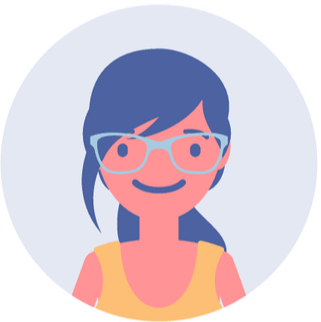
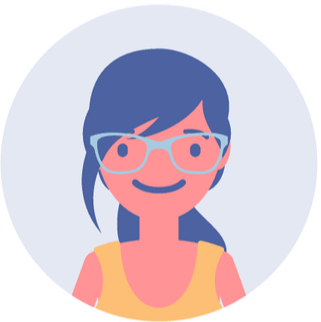
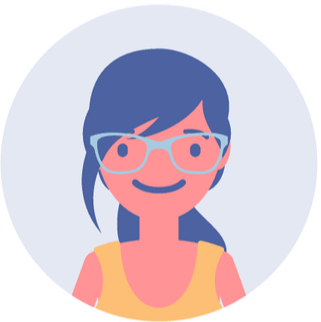
外国人夫が嫌がるから、他の人がいる場や家族団らんの場では「一人一言語の原則」を徹底できないのよね...
という人を何人か見てきました。(「一人一言語の原則」については次章で説明しますね。)
さらに、3番目の「子供たち自身が日本語を学ぶ意義を見い出すこと」が重要だなと思ったのが...
長男が中学1年生だった時、一度は嫌になってしばらく休んでいた日本語補習校に自ら「行きたい」と言い出し、再び補習校に通い始めたという大きな変化がありました。
ちょうど年齢的(13歳)にも、自分が日本人であることを再認識し、日本語を勉強する意義が自分なりに分かってきたみたいです。
現地校でも、先生やクラスメートから日本のことを聞かれて話したりすることが増えてきていたようです。特にフランスでは日本の漫画やアニメが大人気で、日本食をはじめとし日本文化に興味津々の人が多いこともあってか、クラスメートたちから「日本人ってかっこいい」みたいな扱いを受けるそうです(笑)。



これ、フランス在住のママさんたち、皆言ってます!
長男は、フランスのバカロレア(フランスの高等学校教育修了認証試験)での加点を狙って外国語(LV3)を日本語にしているので、それもあって日本語学習のモチベーションがキープできています。
13~14歳頃から日本人としての自己認識が現れ、日本語を学ぶ意義を考えたり、分かり始めたりするようになるというのはどこかで読んだことがありましたし、多くの先輩ママさんたちが言っていましたが、「こういうことなんだ!」と身をもって感じました。
それまでは、何度も補習校を辞めたいと言い出し補習校の先生や他の保護者の方に相談したり、褒めたり、励ましたり、泣かせたり、なだめたり...ずっとバトルの連続だったのに、大きな進歩でした。それ以降、長男とは心穏やかに楽しく日本語の勉強ができるようになっています。



現在中学2年生の次男とは長らくバトル状態が続いていましたが、次男も最近やっとこのステップに達してくれた印象です。
それでは、次章より、バイリンガル教育をうまく進めるための注意点(一般に言われていること)、また、継承語として日本語を学ぶにはどういった場や方法があるのか、我が家の試行錯誤や経験も交えながら、ご紹介していきますね。
バイリンガル教育の基本? 「一人一言語の原則」


「一人一言語の原則」とは?
お子さんを、父の母語と母の母語の両方が話せるバイリンガルにしたい場合、
一人一言語の原則(one person(parent) one language)
が一般的によく知られた方法です。



我が家の場合だったら、父親はいつもフランス語だけで子供に話し、母親はいつも日本語だけで話すことを徹底するという方法です。
(父親は絶対に日本語を混ぜない、母親は絶対にフランス語を混ぜないことがポイント。)
「一人一言語の原則」を徹底すると、子供は、2つの言語間で混乱することがなく、父親にはフランス語で話しかけるようになり、母親には日本語で話しかけるようになるというもの。
外国人配偶者が日本語をまったく理解せずどれだけ寂しい思いをしようと、家庭外であっても、子供の現地校の友人が家に遊びに来た時でも、いかなる状況であっても、「一人一言語の原則」を貫くことが重要と言われています。
実際、みな「一人一言語の原則」を徹底できているの?
うちの子たちは、カナダとドイツの2つの国で日本語補習校に通った経験(長男8年、次男6年)があるので、これまで多くの国際結婚家庭のお子さんを見てきましたが、(補習校にお子さんを通わせる親御さんは一般的に日本語教育について熱意がある方が多い、という事実があるにせよ、)ほとんどのご家庭が「一人一言語の原則」を貫いておられます。



すごいなぁと思います。
なぜなら、我が家は挫折してしまったから。
最初は、夫はフランス語、私は日本語と決めてやっていたのですが、長男は3歳ぐらいまでほとんど言葉が出て来ませんでした。まわりからは心配され、私も他のお子さんと比べたりネットで検索したりして焦ってしまって、結局夫とも話し合って、しばらくは思考のベース言語としたいフランス語をきちんとしようということで、フランス語のみにすることにしました。
その後は、同年齢のお子さん同様フランス語力は伸びていき、学校での勉強にも支障がなく...今振り返ると、焦らず長い目で見ればよかったと思います。
私の母に聞いたところ、私も小さな頃はあまり話さず、注意深く色々なことを観察する、慎重な性格だったようで、まさに長男はそんな感じなので、多言語環境+発語が遅めの男の子であることに加え、遺伝的な部分もあったのかもしれません。
「一人一言語の原則」を諦めてしまった我が家ですが、日本語力がついてきた今、(家族団らんの場ではやっぱりフランス語が優勢になってしまいますが、)私が子供たちに日本語で話すとちゃんと日本語で返してくれますし、夫がいない時は子供たちのほうから進んで日本語で会話しようとしてくれるので、まぁよしとします。
海外にいながら子供たちが日本語を学ぶのって、親と子の気の長い「バトル」の連続だと思っているので、最近は肩の力を抜いてやっています。
「起きている時間の30%」ルール
カナダに住んでいた時、アルバータ大学で継承語研究をされている社会言語学のMartin Guardado教授が、日本語を継承語として教える親を対象にセミナーをされたので参加しました。
その時、子供をバイリンガルにしたければ、
起きている時間の少なくとも30%の時間、弱い方の言語(継承語)に触れる時間を確保しないといけない
というお話をされました。
1日9時間寝るとして、起きている時間の30%は4時間半。
つまり、平日は現地校があるから、現地校からの帰宅後の時間のほとんどを日本語で過ごさないといけないってこと!?
お子さんがまだ幼稚園や学校に通っていない時期であってもフルタイムで仕事をされている親御さんにとっては難しいでしょうし、子供が大きくなると現地校の宿題も増えてくるので家で日本語ばかりやってられません。
週末にキャッチアップするとしても、しんどい数字です。
継承語が2つ以上あったら到底無理ですね...
言語学習においては、その言語に触れる時間が長ければ長いほど上達が速いのは確かですが、あくまで「理想」。



30%の時間を確保できないなら、工夫して「量より質」を重視するしかないですね。
コミュニケーション重視型の方が言語発達レベルが高くなる
同じく前述のセミナーの時に、もうひとつ興味深い話を聞きましたので、ご紹介します。
例えば、お子さんが日本人のお母さんに向かって英語でこう言ったとします。
Mom, I want to eat cookies.
それに対して、お子さんに日本語を話してほしいお母さんはどう答えたらよいのでしょうか?
A: 日本語で話しなさい!
B: わからない、何?
C: ん?クッキー食べたいの?
Aは、お母さんが一生懸命になるあまりに、日本語で話すことを強制、命令してしまい、コミュニケーションを阻止してしまうパターン。Guardado教授によると、これが実際一番多いパターンだそうです。
Bは、子供が日本語以外で話しかけてきたら分からないふりをすることで子供に日本語で話すことを促すパターン。これもコミュニケーションをストップしてしまいます。
Cは、ポジティブな結果をもたらすコミュニケーション重視型で、A~Cの中ではお子さんの言語発達レベルが一番高くなるそうです。
さらに、AとCを組み合わせたパターンDもあります。
D: ん?クッキー食べたいの?ちょっと日本語で言ってみようか!?
Dは、命令口調というより会話口調で、日本語を使ってみようという意識を高めることができる、一番おすすめのパターンだそうです。



私自身、子供たちがなかなか思うように日本語を覚えてくれなくてイライラした時など、AやBになってしまっていることもあったので反省したのでした。
海外で日本語を学べる場


海外でも日系の保育園や幼稚園があれば利用するのも一案
ネットで調べてみると、世界各地(もちろん大都市限定ですが)に日系幼稚園があります。
長男が小さい頃「一人一言語」を諦めたと上に書きましたが、長男が3歳になってフランス語力がどんどん伸びるようになってから、このままでは日本語が全然話せなくなってしまう、何かきっかけが欲しい、と思っていました。
ちょうど台湾にしばらく住む予定を立てており、調べてみると、台北に日系幼稚園があるではないですか!
というわけで、博如日本幼稚園(Hiroka Japan)に2年弱お世話になりました(長男4~6歳、次男2歳~4歳)。
おかげで、子供たちはある程度自然に日本語が口から出てくるようになりました。
また、子供たちが幼稚園で日本の行事を経験でき、日本語を話す遊び友達ができたこともよかったです。
日系の保育園や幼稚園に入ると現地語に遅れがでないか心配、という方がいらっしゃいますが、現地語にはその後いやでもどっぷり漬かりすぐに追いつくので、心配ないですよ!
それよりもこの時期に日本語をある程度身に着けておくことのメリットの方が大きいと思います。
日本語補習校や、継承語としての日本語教育機関を利用しよう
「日本人学校」「日本語補習校」「継承語としての日本語教育機関」 の違い
まず最初に、海外でお子さんが日本語を学べる教育機関の種類について整理しておきましょう。
それぞれ、設立の目的が異なることがポイントです。
- 日本人学校
-
もともと日本人駐在員子女の教育を目的に設立された、平日の全日制の学校。文部科学省が管轄。
- 日本語補習校(日本語補習授業校)
-
日本政府の定める教育課程に沿った授業(通常、国語と算数/数学。社会や理科を教える補習校もある)を日本語で行い、海外在住の児童・生徒が将来日本の小学校または中学校の授業に十分適応できうるだけの学力養成を目的に設立された学校。日本政府からの財政援助あり。
授業は、週末や平日の放課後。
以前は両親いずれも日本人の子も多かったが、現在では国際結婚家庭の子が増えている。日本人学校がない地域では、日本人駐在員子女も通っている。
- 継承語としての日本語教育機関
-
継承語としての日本語教育を通して、海外に在住する子供達に日本人としてのアイデンティティーを残すことを目的に、有志によって設立された日本語教育機関。
授業は、週末や平日の放課後。
ほとんどが国際結婚家庭の子。
補習校、または、継承語としての日本語教育機関の利用をおすすめする理由
平日に現地校に通う国際結婚家庭のお子さんが利用するとしたら、
- 平日の放課後または週末に授業を行う補習校
- 継承語としての日本語教育機関
のどちらか、になります。
日本語補習校、継承語としての日本語教育機関のリストは、お住まいの地域を管轄する大使館・総領事館のサイトに掲載されていることが多いです(「子女教育」「教育機関」「教育施設」といったページに掲載されています)。
もしご自宅から通える範囲にあるなら、通われることをおすすめします(もし通える範囲にないなら、オンラインで授業を受けられる補習校もあります。オンライン補習校については後述しますね)。
というのも、海外で、家庭内に自分しか日本語を母語とする者がいない環境で、子供たちに日本語教育をやっていくというのは、本当に長く孤独な闘い(笑)だからです。
親の力だけでは大変です。
ほとんどの親は教員免許を持っていませんし、教えるプロではありません。



補習校の授業参観に行くと、「さすが教育のプロ!海外在住のお子さんのこともよくわかってらっしゃる。私はあんな風には教えられない。」って思う先生が多かったです。
親はつい感情的になってしまうことも多く、先生やお友達といっしょの方が楽しく学べるという場合が多いです。
何より、学校を通じて他のお子さんと知り合うことができ、学校の休み時間にいっしょにサッカーをしたりして遊んだり、学校以外でもいっしょに遊んだりと、日本語を使う機会を増やせます。
親だって、他の保護者と知り合いになれ、有益な現地情報を交換できたり、日本語教育の悩みを相談できたりします。
うちの子たちは、毎週土曜日、幼稚園の時は継承語としての日本語教育を行う「日本語センター」に通い、小学1年生から日本語補習校に通いました。長男も次男も、日本語センターから数えると9年間、こういった日本語教育機関のお世話になりました。
2人とも補習校を辞めたい(長男はしばらくお休みした)時期がありましたが、なんとか乗り越えました。
山あり谷ありでしたが、今の子供たちの日本語力があるのは、日本語センターと補習校のおかげです。



少なくとも私は、もし補習校や日本語センターなどがなければ、とっくの昔に挫折していたと思います。
日本語補習校についてもっと詳しく知りたい方
補習校のメリット・デメリットなど、うちの子たちが通った2つの補習校での体験談も交えながら、別記事にくわしくまとめています。
- 補習校って行く必要あるの?と思っておられる方
- お子さんを補習校に行かせるかどうか迷っている方
- 「宿題が辛い」「現地校との両立が大変」とか色々な噂を聞くけど、実際はどうなんだろう?と思っておられる方
に参考にしていただけると思います。
コロナ禍以降、オンラインの日本語補習校も人気
家から通える範囲に、日本語補習校や、日本語を継承語として教える教育機関がない場合、オンラインで授業が受けられる日本語補習校を利用するという手もあります。
コロナ禍の影響で、オンライン授業に対する私たちの精神的ハードルが下がりましたし、オンライン授業ならではのメリットに気が付いた人も多かったようです。コロナ禍以降、ここ3年で、オンラインの日本語補習校に通うお子さんが急増し、現在でも申込者が多い、とオンラインの日本語補習校を運営しておられる方が仰っていました。
補習校などは土曜日に授業を行うところも多いですが、オンラインの日本語補習校は、原則どこも平日の夕方~夜に授業を行っているので、週末に音楽やスポーツなどの習い事ができたり、家族でゆっくり過ごしたり、週末を有意義に使えます。
オンライン補習校についてもっと詳しく知りたい方
オンライン補習校には、実は他にもたくさんのメリットがあります。
オンライン補習校について詳しく知りたい方は、別記事をお読みください。
(アメリカ、カナダ、ヨーロッパなどから参加できる、おすすめのオンライン補習校も紹介しています。)
海外のお子さん (幼稚園~小学生低学年) におすすめの教材
幼稚園の時は「こどもちゃれんじ」がよかった
我が家では、子供たちが幼稚園の時は、ベネッセの「こどもちゃれんじ」をやっていました。
「しまじろう」の「こどもちゃれんじ」です。
読み聞かせ用教材あり、ドリルあり、付録教材(知育教材)あり、保護者用読み物ありで、内容盛りだくさん。うちの子たちは届くたびに喜んで開封し、ドリルに取り組んだり、知育教材で遊んだりしていました。付録で付いてきたお風呂の壁に貼るポスター(カタカナ、漢字、世界地図など)もよくできていて、我が家ではボロボロになるまで活用しました。



日本の幼児教育教材は本当によくできているなと感心したものでした。
もし海外からでも入手できるようであれば、こういった幼児教育教材を利用して日本語に触れる機会を増やすのもおすすめです。
「こどもちゃれんじ」は海外まで送ってもらうと高い! 安く入手するには?
「こどもちゃれんじ」を日本国内で受講する場合は、例えば年少さんなら月々2,460円、年中・年長さんなら月々2,730円(いずれも2023年10月号から入会の場合の、12ヶ月分一括払いの料金。送料・税込)なので妥当な金額です(というか、あの内容でこの料金。海外在住者からすればうらやましい価格設定ですよね)。
ですが、海外まで送ってもらうとなると、配送料を含める分高くなってしまうんですよね。
【例】日本→アメリカ/カナダまで送ってもらう場合の海外受講費
- 年少さん・・・月々6,223円(=42 US$)
- 年中・年長さん・・・月々6,405円(=43 US$)
※2023年9月現在の受講費(送料・税込)
>>「こどもちゃれんじ」をお住まいの国まで送ってもらう場合の海外受講費はこちら(ベネッセ海外受講サイト)でご確認ください。
そこで、海外在住者は実際どうしているかというと...カナダに住んでいた時、まわりに結構「こどもちゃれんじ」の受講者がいたのですが、ほとんどの人は国内受講にしていました。日本の実家に送ってもらって、2~3ヶ月に一度在住国まで送ってもらったり、一時帰国する時に持って来たりしていました。



国内受講で一学年上の教材を申し込んでおいて、一時帰国した時に実家から一年分まとめて持ってくる、という人もいました。
なるほど!
<海外受講にすると、こんなことも>
我が家は、「毎回親の手を煩わせるのもなぁ」「高いけれど子供が喜んでいるし、まぁいいか」と一時期直接海外まで発送してもらっていたのですが、ひとつ小さな問題がありました。
検疫の都合で、種は日本から海外へ送ってもらえないのです。例えば「こどもちゃれんじ」年長さんの付録教材「おじぎそうセット」は種なしで送られてきました(種だけ、事前に登録しておいた国内連絡先(実家)に送ってくれます)。
幼児教育教材は、お子さんに合うかどうか実際に試してから申し込むのがおすすめ
「こどもちゃれんじ」は、絵本やワーク見本など結構立派な無料体験教材セットを送ってくれるので(ただし、日本国内にしか送ってくれないので、宛先を実家住所などにしましょう)、興味があればまずは無料体験教材セットを送ってもらうことをおすすめします。
大体どこも無料体験セットや資料を送ってくれるので、私は他にもZ会など数社に資料請求してみてから決めました。
しまじろうって独特なキャラクターだし、実際試してみてお子さんの反応を見てみるとよいと思います。
最新情報の確認、無料体験教材セットの申込は「こどもちゃれんじ」の公式サイトからできます(「無料体験教材・資料請求」リンクから)。
ちなみに、ベネッセの「こどももちゃれんじ」は幼稚園の年長で終わり、小学1年生からは「進研ゼミ」になります。「こどもちゃれんじ」が好きだった長男は「進研ゼミ」もしばらくやっていたのですが、毎週土曜日に日本語補習校に通い始め、余力&受講するメリットがなくなったので止めました。
小学校低学年にはオンライン教材「すらら」がおすすめ
次男が小学校高学年の時、訳あって日本語補習校を辞めさせようかと思っていたことがあるのですが、その時(オンラインの日本語補習校も嫌だと言うので、)何か楽しく日本語学習を続けられる教材はないかと本気で探しました。
その時、同じく国際結婚家庭で日本語教育を頑張っている友人から勧められたのが「すらら
実際、次男は小学6年生の時にすららを受講したのですが、小学校低学年~高学年途中までの範囲を楽しく復習できました。次男の受講体験を通して、すららは海外在住の国際結婚家庭のお子さん(特に小学校低学年のお子さん)にぴったりだと思いました。
ちなみに、すららでは小学1年生から学べます(幼稚園コースはありません)。例えば、小学生の4教科コースは月々8228円(税込)からなんですが、この料金に、小学1年生~6年生の6年分の国語・算数、小学3年生~6年生の4年分の理科・社会の内容がすべて入っていて、毎月好きなところから好きなところまで学べる、というシステムなんです。



最初に月額料金を見た時高いかな~と思ったのですが、よく考えると日本語補習校の月々の授業料はその倍以上だったし、オンライン日本語補習校の月々の授業料も小学生だと国語の一教科(週に100分)だけで月々13,000~17,000円ぐらいが相場。
楽しく勉強を続けられて効果があるなら払えない金額ではないと思い直しました。
すららが海外在住の国際結婚家庭のお子さんにぴったりだと思う理由
すららが海外在住の国際結婚家庭のお子さんにぴったりだと私が思う理由は主に次の3つ。
- 自由度が高い「無学年式」教材
例えば「小学生4教科コース」だったらいつでも小学1年生~6年生の6年分の国語・算数、小学3年生~6年生の4年分の理科・社会の範囲内の好きな内容にアクセスでき、毎月自分の学力に合わせて自分のペースで学べる、というシステム。
(「小学1年生の9月に学ぶべき内容を、小学1年生の9月に学びましょう」という「学年式」教材ではない。)
→日本の子供と同じスピードで学ぶことができない、海外在住のお子さんにぴったり。 - クラウド教材なので専用タブレットが不要
「自宅のパソコン・タブレット」と「インターネット環境」の2つがあれば受講できるので、思い立ったらすぐ受講できる。専用タブレット教材につきもののペナルティがなく、1~2ヶ月だけの受講もOK。
→どんな教材が自分に合うかわからない、気軽に受講してみたい海外在住のお子さんにぴったり。
※「チャレンジタッチ」「スマイルゼミ」などは専用タブレットが必要で、そもそも海外での受講者を対象にしていない。専用タブレットは海外まで送ってもらえないし、日本で入手して海外に持って来たとしても万が一の破損や不具合の場合に対応してもらえない。また、短期間の受講で退会した場合ペナルティが発生する(専用タブレット代金が請求される)ので1~2ヶ月だけの気軽な受講ができない。 - 好きな時に休会できる(月単位)
例えば「夏休みの2ヶ月間は休会」「現地校の勉強が大変だから来月は休会」という感じで柔軟に受講月を調整できる。(オンラインで簡単に何度でも休会・再開の手続きができる。)
→現地校と習い事、日本語学習のバランスを取るのが難しいことがある海外在住のお子さんにぴったり。



アニメキャラクターが楽しい講義をしてくれる。
AI搭載型ドリルなのでつまづきポイントがわかる(AIができるまでしつこく質問してくる)。
ゲーム感覚でやる気が出る仕組みがある。
などなど。
すららのおすすめポイントは他にもあるのですが、それは公式サイトを見たり資料請求したりすればわかることなので、私はあえて海外在住者ならではのおすすめポイントに絞ってみました。
すららを特に「小学校低学年の」お子さんにおすすめする理由
アニメキャラクターが教えてくれるインタラクティブな講義で、ゲーム的な問題も用意されているので、特に小学校低学年のお子さんは楽しんで学習できます。



すららの講義は公式サイトから無料体験できるので、お子さんの反応を見るために、まずは実際にお子さんと無料体験してみるとよいですよ。
うちの次男は、小学6年生で受講したので「ちょっとアニメキャラクターが子供っぽい」とかぶつぶつ言ってましたが、低学年範囲の国語のゲームなどを楽しんでやり、「もっと小さい時にこういうので勉強したかったな~」と言っていました。



実際、すららの受講者は小学校低学年のお子さんが多いそうですよ。
また、うちの次男と同じように、もう一度小学校低学年の範囲からきちんと学習し直したい、というお子さんにもよいと思います。(うちの次男は一応小学校の6年間日本語補習校に通って日本の教科書に準拠した内容を学習したのですが、繰り返し学習、深堀り学習が圧倒的に不足していました。)
すららをお得に申し込む方法
すららはランダムに入会金無料キャンペーンをやっています。申込月によって、本来7,700円または11,000円(2023年9月現在)の入会金が無料になるので、これは結構大きいです。



2023年9月は入会金無料になってないので、10月は入会金無料になるのではないかと予想しています。
ちなみに、月途中の申込は月額を日割り計算してもらえます。
私は最初申込を迷っていたこともあって、とりあえず資料請求(海外在住者は郵送ではなくデータで送ってもらえる)してみました。私の時は、資料請求後に希望者が参加できるオンライン説明会があって、それまで抱えていた疑問が解消され、また、オンライン説明会参加者特典付きで入会できたのでラッキーでした。(すらら公式サイトで資料請求ができます。)
海外で日本語力を伸ばすために家庭でできること


幼児期~小学校低学年はとにかく日本の絵本・児童書の読み聞かせを
お子さんが小さい時の絵本の読み聞かせには、多くのメリットがあることが知られています。
日本語の言語能力だけでなく、想像力や豊かな感情を育むことができます。
実際、長男が補習校に入学した時、1年生の担任の先生から
「お母さん方、とにかくご家庭でしっかり読み聞かせをしてあげてください!」
と言われました。
日本では、幼児期から小学校低学年にかけて読み聞かせをするとよいと言われていますが、海外在住のお子さんは日本語の語彙力、読解力が劣っているので、子供が嫌がらなければ小学校高学年でも続けてもいいと思います。
海外だと、どこで日本の絵本や児童書を入手するかが問題ですが、通常、お子さんが補習校や継承語としての日本語教育機関などに通っていれば図書館を利用できます。「1回の貸し出しは3~4冊まで」といった具合に一回の貸出冊数に制限がありますが、それでも毎週違う絵本や児童書を借りることができるのはありがたかったです。あとは、お住まいの都市によっては、日本人会の図書館が利用できる場合がありますね。
我が家では、小学低学年までに、日本でのロングセラー絵本や、日本の子なら誰でも知っているだろう日本昔話や世界の童話などを一通り読み聞かせました。
絵本を海外まで送ってもらうと送料が高くつくので、一時帰国時に日本で買って持って来るという人も多いと思います。
絵本を選ぶ際、「絵本ナビ」という日本最大級の絵本・児童書情報サイトはとても便利ですよ。
「絵本ナビ」でわかること、できること
- お子さんの年齢やテーマに合った絵本がわかる。
- 各絵本についての保護者の口コミがたくさんあり、選ぶ際の参考になる。
- 購入前に絵本の試し読みができる(各絵本1回のみ)。無料で一冊丸ごと全ページ試し読みできる絵本が2200冊以上。無料メンバーは月3冊まで全ページの試し読みができる。有料のプレミアムメンバーは冊数無制限で全ページの試し読みができる。メンバー登録しなくても「ちょっとためしよみ」で数ページ読める絵本が1万冊以上ある。
- 「絵本クラブ(EhonClub)」(年齢別に厳選した絵本の定期購読サービス)に申し込めば、海外まで定期的に絵本を送ってもらえる。※コロナ禍以降、ほぼ全世界でサービス停止中(韓国、台湾、ベトナム、メキシコのみEMS便で再開)。



海外在住だと、図書館や本屋さんで絵本を手にとってぱらぱらっと中を見てみるということができないので、どんな絵本が年齢に合っているのか、どんな絵本を買えばよいのか迷いますが、このサイトで解決します。
音読を習慣づけると、日本語の読解力や語彙力が向上する
日本語補習校で必ず毎週出される宿題といえば「音読」。
「な~んだ、音読か...」と思われたかもしれませんが、音読を継続することの効果は大きいです。
うちの子たちは、補習校の宿題として出されたことをきっかけに、小学1年生から音読を始めました。
小学校低学年で音読の宿題は終わると思いきや、その後も小学校卒業までずっと補習校の宿題として出され続け、平日の夜の音読はすっかり我が家の習慣となり、音読タイムは母子の大事なコミュニケーションタイムとなりました。
音読する内容が難しければ1日1ページでもいいんです。毎日、無理のない量を読むことが長く続けられるコツです。あとは、音読内容に出てきたものをネットで検索して画像で確認したり(日本の子供たちが普通に知っているものでも海外在住の子供が知らないものって結構あるんですよね)、関連動画をYouTubeでいっしょに観たりすると、興味が持てるし理解も深まるのでおすすめです。(ちなみに、数年前から、国語の教科書にはQRコードが付いていて、動画視聴で理解が深められるようになっています。)
長男が中学生になってからはさすがに音読の宿題は出なくなりましたが、それでもやっぱり音読をすると効果が感じられるので、中学生になっても週1~2回と回数は少なくなりましたが、音読を続けました。
音読をする時は、私は他のことは一切せず、きちんと子供の隣に座って子供たちといっしょに目で文字を追います。(疲れていた時は、ソファで寝落ちしそうになったことも何度かありましたが...)
「音読」というのは、目で文字を追いながら同時に耳から文章を入れることですが、そうすることで、読解力が向上し語彙や言い回しが身に付きやすくなります。すらすら音読できるには、言葉の意味がわかっていなければいけませんし、意味のまとまりを意識しないといけません。次男の音読はたどたどしい時があるのですが、音読している時に変なところで区切ると違和感があることに自分でも気が付いてすぐに読み直します。意味のまとまりを意識しながら、内容を理解しようとしながら読んでいることがわかります。声に出さずに読むと、わからない言葉や読めない漢字を、意識せずに読み飛ばしていたりするんですよね。そばにいて音読を聞いていると、子供が理解できていなさそうな言葉や言い回しが想像できるので、音読が終わったら、わかっているかどうか確認したり説明したりしています。
ちなみに、音読には、脳を刺激し、記憶力をアップさせる効果もあるそうですよ。
音読するものは、我が家の場合、補習校に通っていた時は、たいていは音読の宿題として出された国語の教科書やプリントでした。
ただ、国語の教科書に載っているものの中には、子供が読んでいておもしろくないと感じるものもあります。そんな時は、道徳の教科書や読売KODOMO新聞(オンライン版)などを利用することもできます。
読売KODOMO新聞とは?
日本には、小学生をターゲットにした小学生新聞が三紙(読売KODOMO新聞、毎日小学生新聞、朝日小学生新聞)あります。
三紙のうち読売KODOMO新聞だけが週刊、他の二紙は日刊です。
読売KODOMO新聞は、写真やイラストが多く、三紙のうち一番読みやすく理解しやすいです(一番初心者向け)。漢字にはふりがながふってありますし、海外在住のお子さんにも読みやすいと思います。
(ドイツの補習校では、読売KODOMO新聞記事の音読が宿題として出されることがありました。)
※日本在住者は紙版しか申し込めませんが、海外在住者はオンライン版を申し込めます。
日本のアニメなどを視聴し、語彙を増やそう
あまりお子さんにテレビやタブレット、スマホを見せたくないという親御さんもいらっしゃると思いますが、我が家は時間を決めて子供たちに日本のアニメなどを見せています。
日本のアニメは世界的に人気なので、探せば、英語やフランス語などの吹替え版が見つかりますが、我が家では「日本のアニメは日本語で見る」というルールを決めています。アンパンマン、日本昔話、ドラえもん、妖怪ウォッチ、ポケモン、NARUTO、ワンピース、鬼滅の刃、僕のヒーローアカデミア、名探偵コナン、進撃の巨人などを見てきましたが、日本語の語彙力を増やすのにとても効果があります。
国語の教科書などを音読させていて「この言葉知らないだろうな」と思って尋ねると、「あ、その言葉、ドラえもんに出てきた」「コナンで言ってた」などと言うことも結構多かったです。
ただ、画面から一方的に受け取るだけでは語彙力はつきにくいので、我が家では、アニメを見た後に日本語であらすじや感想を話してもらうようにしています。



勉強という感じにすると嫌がるので、「お母さんもそのアニメにとても興味があるんだけど、今回のエピソードはどんなだったか教えて!」という感じで聞いています。
すると、喜んで話してくれます。
また、日本のバラエティ番組も楽しめるようになりました。芸人同士の掛け合いを理解するにはかなりの日本語力が必要になりますが、日本のバラエティ番組は文字テロップも出るので理解の助けになるみたいです。
次男は「はじめてのおつかい」(年に2~3回放送)や「ザ!世界仰天ニュース」の「イケメン仰天チェンジ」の回などを楽しんでいました。長男は時々「月曜から夜ふかし」などを見ています。(日本のバラエティ番組は、日本での放送後一週間はTVerで無料で見られます。また、「はじめてのおつかい」は、昔(2013年)の放送分ですがNetflixで30話分視聴できます。)
私も時々いっしょに見て、日本語の質問に答えたり、文化の違いなどで理解しにくいかなと思われるところは視聴をストップして説明したりしています。
VPNというセキュリティ技術を使えば、海外からでも「TVer」(無料。主にバラエティ番組)を視聴できます。
居住国で「Netflix」を契約している人は、VPNを使えば、追加料金なしで日本のアニメが見られます(居住国のNetflixでも日本のアニメが見られますが、日本のNetflixのアニメのラインナップの方が豊富です。特に「ドラえもん」など)。
日本のアニメ、キッズ番組の配信数が多い「U-NEXT」を契約している人は、海外からでもVPNを使って視聴できます。
日本へ一時帰国した時にできること (小学校の体験入学など)


日本への一時帰国は、海外在住の国際結婚家庭のお子さんの日本語力を伸ばし、お子さんが日本にさらに興味を持ち日本のことが好きになる絶好のチャンスですよね。
我が家では、コロナ禍前の話ですが、夏休みに2~3週間程度、日本の小学校(私の母校)に体験入学させてもらいました。(カナダの夏休みは日本より3週間半ぐらい早く始まりますし、夏休み開始直前の現地校はほぼお遊び状態(?!)ということで、まわりには1ヶ月ぐらい日本の小学校に体験入学させてもらっているお子さんもいました。)
体験入学は日本ならではの素晴らしいシステムなので、もし学校側が受け入れてくれるなら是非試してみられることをおすすめします。(ただ、あくまで厚意で受け入れてくださっていることを忘れず、学校や先生にできるだけご迷惑をおかけしないよう保護者として最大限の準備とサポートをしてくださいね。そうすると、毎年快く受け入れてもらえると思います。)
海外で補習校に通っていても体験できないこと、例えば、水泳や音楽、図工などの授業、給食や掃除、休み時間の遊び(縄跳び、鉄棒、一輪車、竹馬など)、交通安全教室、子供たちだけでの集団登下校などを体験できます。
1年に2~3週間だけなので完全に「お客さん扱い」され、ちやほやされているというのもありますが、子供たちはとても楽しいらしく、最後はお友達と涙・涙のお別れ...そして、今でも時々楽しかった日本の体験入学の思い出話をしています。
体験入学以外では、毎年のように国語の教科書に戦争の話が出てくるので、広島や長崎に足を運んでみるのもよいと思います。次男は小学5年生の時に国語の授業で習った落語が気に入っているので、もし生で「初天神」や「寿限無(じゅげむ)」が観られる機会があるなら寄席デビューするのもよいなぁ、と考えています。
最後に
というわけで、とても長くなってしまいましたが、我が家の日仏家庭生まれの子2人の日本語教育について私が考えてきたこと、実際に試してよかった教材、実際にやってきて効果があったこと、海外にいながら日本語を学べる場や方法などについてご紹介しました。
とは言っても、これはあくまで我が家のやり方であって、各ご家庭の言語環境も異なるでしょうし、100家庭あれば100通りの日本語教育のやり方があると思っています。
私自身、これまで10年以上あれこれ試行錯誤しながら、子供たちと日々「バトル」しながら今日まで来ました。
「他の方たちはどうやってお子さんの日本語教育されているんだろう?」と思いネットで検索し、新たな気づきやヒントを得られたこともありました。
この記事で何か参考にしていただけることがあったなら嬉しいです。
超長文記事を最後までお読みいただきどうもありがとうございました!