こんにちは!フランス在住のKokoです。
海外に住んでいても、日本国籍をもつ小学1年生~中学3年生(日本での学年が基準)のお子さんは、無料で日本の教科書を入手できるということはご存じでしょうか?
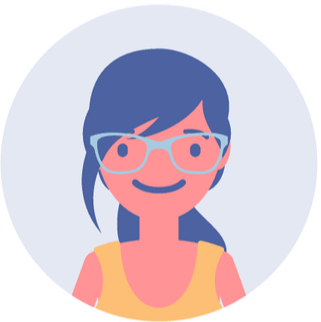
日本人学校や補習校に通っていなくても、もらえるの?
申込時期や申込の方法が知りたいな。
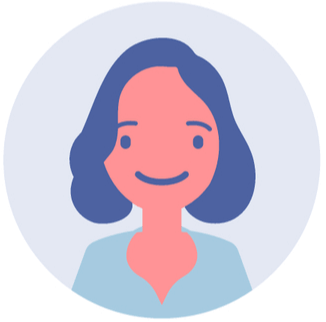
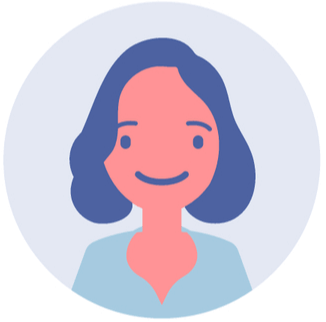
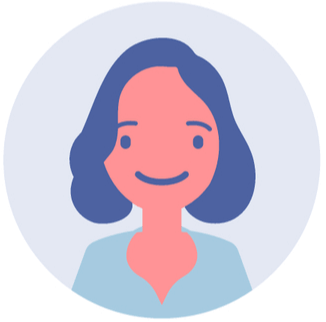
どんな教科書がもらえるの?
教科書の出版社って日本国内では色々あるけど?
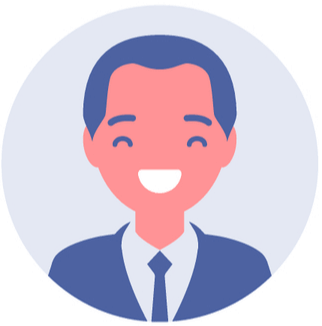
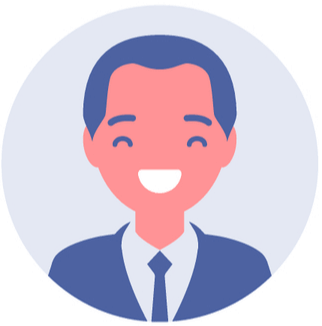
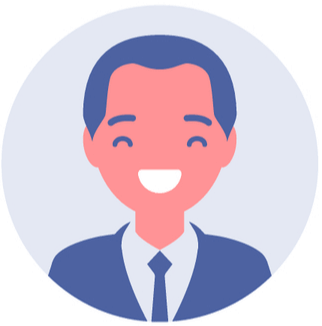
希望する科目の教科書だけもらえるのかな。
本来の学年と違う学年の教科書がもらえるかな。
本記事では、このような疑問にお答えします。
海外で日本の教科書が無料でもらえる子供の条件
日本ではあまり知られていませんが、日本政府は、海外在住の、義務教育学齢期にある日本国籍をもつ子供たちに、日本の教科書を無償で配布しています。



海外で生まれ育ったうちの子2人も、小学校1年生の時からずっと、日本の教科書を無料でいただき、日本語補習校や自宅で、国語や日本式の算数を勉強してきました!
教科書が無料でもらえる条件とは?
海外で日本人学校や日本語補習校に通っていなくても、1) 以下の条件を満たしていて、2) 定められた申込受付期間内に管轄の大使館・総領事館に申込を行えば、誰でも日本の教科書の無償配布を受けられます。
- 日本国籍を持っている(もちろん日本国籍を含む重国籍者もOK)。
- 日本の義務教育学齢期(小学1年生~中学3年生)の子供である。(※下に学齢早見表があります。)
- 管轄の大使館・総領事館宛に「在留届」を出していて、教科書無償配布を受ける子供が「在留届」の「同居家族」として登録されている。
- 在住国に長期滞在中。
- 永住者の場合、将来日本で進学(または就労)する意思を持っている。
永住者は教科書無償配布の対象にならない?
永住者で「将来日本で進学または就労する意思をもたない」場合は、日本の教科書の無償配布を受けることはできないとされていますが、実際に、大使館・総領事館が申込受付時にその点について確認することは難しいですよね。
というわけで、この条件は気にされなくてもよいかと。
私のまわりをみると、両方または一方の親が日本人で日本と繋がりのあるお子さんたちは、日本に興味があり、大きくなって、日本で勉強をしたり、日本で就労したりというケースも少なくないですが、小学生の時にそういった意思をはっきり持っていたかと聞かれると、どうなんでしょうね。
いずれにせよ、多くの永住者(国際結婚家庭)のお子さんが、日本の教科書の無償配布を受け、日本語補習校で授業を受けたり、家庭で日本人のお父さんお母さんと日本語の勉強をしたりしています。
「学齢早見表」で子供の日本での学年を確認しよう
海外の学校は8月~9月に新学年が始まるところが多く、4月始まりの日本とは学年が半年ずれています。
日本人学校や補習校に通っていないと日本の学年で何年生なのか分からなくなりがちですよね。
お子さんの日本での学年がわからない方は、次の学齢早見表で日本での学年を確認できます。
今後申込できる教科書についてのスケジュール (①2024年前期用&通年用教科書、②2024年後期用教科書)
以下に、今後申し込みできる2期分の教科書申込受付時期などをまとめてみました。



申込を考えておられる方は、お子さんの学齢による申込受付時期を確認し、タイミングを逃されませんように!
①2024年度前期用&通年用教科書申込のスケジュール&学齢早見表
2024年度前期用・通年用教科書(2024年4月から使用する教科書)の申込対象者、申込受付時期、教科書配布時期は次の通り。
- お子さんの学年が小学1年生~中学3年生(2009年4月2日~2018年4月1日生まれ)
- 申込受付時期は2023年9月頃
- 教科書配布時期は2024年3月頃
2023年9月27日現在、一部の大使館・総領事館ではすでに締め切られていますが、一部の大使館・総領事館ではまだ受け付けられています。



例えば、在フランス大使館は2023年9月20日締切、在アメリカ大使館は2023年9月29日締切、在オランダ大使館は2023年10月11日締切、とばらばらです。
申込締切日は、大使館・総領事館によって多少前後しますので、直接お住まいの地域を管轄する大使館・総領事館に問い合わせてみてください。
ちなみに「通常申込」の受付は終了していますが「追加送付」の申込は可能です(「追加送付」の場合、教科書自体は無料ですが、送料及び手数料は自己負担)。詳しくはこちらの記事をお読みください。
| 2024年4月からの 日本の学年 | お子様の生年月日 |
|---|---|
| 小学1年生 | 2017年4月2日 ~2018年4月1日 |
| 小学2年生 | 2016年4月2日 ~2017年4月1日 |
| 小学3年生 | 2015年4月2日 ~2016年4月1日 |
| 小学4年生 | 2014年4月2日 ~2015年4月1日 |
| 小学5年生 | 2013年4月2日 ~2014年4月1日 |
| 小学6年生 | 2012年4月2日 ~2013年4月1日 |
| 中学1年生 | 2011年4月2日 ~2012年4月1日 |
| 中学2年生 | 2010年4月2日 ~2011年4月1日 |
| 中学3年生 | 2009年4月2日 ~2010年4月1日 |
②2024年度後期用教科書申込のスケジュール&学齢早見表
2024年度後期用教科書(2024年10月から使用する教科書)の申込対象者、申込受付時期、教科書配布時期は次の通り。
- お子さんの学年が小学1年生~5年生(2013年4月2日~2018年4月1日生まれ)
- 申込受付時期は2024年3月~4月頃
- 教科書配布時期は2024年9月頃
小学6年生~中学3年生のお子さんについては、教科書の申込は一年に一回だけで、後期用教科書の申込はありません。
| 2024年4月からの 日本の学年 | お子様の生年月日 |
|---|---|
| 小学1年生 | 2017年4月2日 ~2018年4月1日 |
| 小学2年生 | 2016年4月2日 ~2017年4月1日 |
| 小学3年生 | 2015年4月2日 ~2016年4月1日 |
| 小学4年生 | 2014年4月2日 ~2015年4月1日 |
| 小学5年生 | 2013年4月2日 ~2014年4月1日 |
海外の子供たちに配布される教科書の種類、出版社、配布頻度・時期


小学4年生までは上下巻に分かれているが、小学5年生からは通年の教科書に。
日本では、各都道府県や市区町村の教育委員会が公立の小中学校で使用する教科書を採択していますが、海外で配布される教科書は全世界共通です。
例えば、小学生の国語は「光村図書」、小学生の算数は「東京書籍」というように、海外では、各科目について日本国内で最も需要がある出版社の教科書が配布されています。
教科書の種類・出版社の確認方法



日本から海外へ子連れで赴任するのだけど、子供たちが通うことになる日本人学校や日本語補習校で使用している教科書の出版社を知りたい。
今日本の学校で使っているのと同じ教科書を使用するのかな。



今、海外に住んでいるけれど、夏休みに日本の小学校で体験入学をする予定。
海外で配布されている教科書の出版社と、日本の小学校で使っている教科書の出版社を調べて、同じ出版社のものだったら日本に持って行きたい。
というような場合。
海外で配布される各学年の教科書の種類と出版社は、
「海外子女教育振興財団」作成の「令和5年度 海外子女用教科書の出版社一覧表」
で確認できます。(令和5年度=2023年4月~2024年3月)
ただし、文部科学省のルールで、日本人学校については、通常海外で配布されている教科書と違う教科書を使用することも許されているようですので、念のため、通うご予定の日本人学校に確認された方がよいでしょう。
日本の小中学校で体験入学の予定がある方へ
日本の公立小中学校で使用されている教科書の出版社は、各市区町村のホームページで確認できる場合が多いです。
教科書の配布頻度と配布時期
教科書の配布頻度・時期は次の通り。
| 日本の学年 | 配布頻度 | 配布時期 |
|---|---|---|
| 小学1年生 ~ 小学5年生 | 年2回 | 前年度の3月頃、 該当年度の9月頃 |
| 小学6年生 ~ 中学3年生 | 年1回 | 前年度の3月頃 |
他の学年の教科書、希望の科目の教科書だけもらえる?
配布される教科書は、お子さんの日本での学齢に応じたワンセットのみです。
- うちの子、日本語が苦手だから、一学年下の教科書がほしい。
- 日本語補習校では、事情があって、一つ上の学年の授業を受けているので、一学年上の教科書がほしい。
- 希望の科目の教科書だけほしい。郵送代が高くつくし、1セット全部はいらない。
というのは、いずれも不可能です。
教科書無償配布の申込から受領までの流れ (個人で申し込む場合)
教科書の無償配布を受けたい場合の、申込から受領までの流れを説明します。
ここで説明するのは、あくまで「個人」で申し込む場合です。
通常、日本人学校や日本語補習校、(継承語としての日本語教育を行っている)日本語センター/日本語教室などにお子さんが通われている場合は、それらの学校が、在校生分の教科書の申込・受領をまとめて行います。
日本人学校、日本語補習校、日本語センター/日本語教室に通い始めたばかりの方は、念のため、次期の教科書申込について、個人で入手する必要があるのか、または、学校側で手配してもらえるのか、学校に確認してみてください。
(時期的に、教科書申込受付時期が終わっている場合は、「ご自身で入手してください」と言われる場合があります。)
管轄の大使館・総領事館宛にまだ在留届を出していない人は、まず在留届を出します。
大使館・総領事館での申込受付時期の目安は、下表の通りです。
教科書は、申し込んですぐにもらえるというものではなく、実際に教科書を使い始める時期の約6か月前に申し込まないといけません。
例えば、日本の小学1年生の教科書がほしい場合は、前年度(お子さんが幼稚園の年長)の9月頃に申し込みを行う必要があります。
| 日本の学年 | 申込受付時期 | 受領時期 |
|---|---|---|
| 小学1年生 ~小学5年生 | ①前期用: 前年度9月頃 ②後期用: 前年度3月 ~該当年度4月頃 | ①前期用: 前年度3月頃 ②後期用: 該当年度9月頃 |
| 小学6年生 ~中学3年生 | 前年度9月頃 | 前年度3月頃 |
申込受付期間は、各大使館・総領事館によって違いますし、同じ公館でも毎年微妙に違います。
(中には、特に申込受付期間を設けず、常時申込を受け付けているという大使館・総領事館もあります。)
管轄の大使館・総領事館のホームページや、在留届提出者に送られてくる案内メールでしっかり確認し、申込受付時期を逃さないようにしましょう!
フランスの日本国大使館・総領事館(在フランス大使館、在マルセイユ総領事館、在ストラスブール総領事館、在リヨン領事事務所)のように、いったん教科書の申込を行い、その教科書を定められた受領期限内にきちんと受領している場合に限り、次回の教科書も継続して申し込むと見なされ、新たに申込書を提出する必要がない、という国もあります。



このやり方は、申込者にとって手間がかからず、いいですね。
ちなみに、
- 申込書のフォーマット
- 申込書の提出方法(来館・メール・郵送・FAX)
- 申込書以外に提出が必要な書類(日本国パスポート、戸籍謄本など)
は、各大使館・総領事館によって異なりますので、ホームページなどで確認してくださいね。
二重国籍のお子さんの中には、「在留国のパスポートはあるけれど、日本のパスポートは作ってない」というお子さんもいらっしゃると思います。
もし管轄の大使館・総領事館が、教科書の申込受付時に日本国籍の確認書類の提示を求めている場合(←すべての大使館・総領事館で求められているわけではありません)、日本のパスポートが提示できなければ、例えば発行後6か月以内の戸籍謄本を提示しなければいけない場合もあります。
戸籍謄本は日本の本籍地役場でしか取得できませんので、入手に時間がかかります。注意しましょう。
受領の方法は、
- 大使館・総領事館の窓口での受領
- 郵送での受領
のどちらかです。
遠方にお住まいの方は「郵送受領」になると思いますが、郵送料は教科書受領者負担です。
ご参考までに、2023年前期用(通年用)教科書の冊数と重量はこんな感じでした。
| 日本での学年 | 冊数 | 合計重量 |
|---|---|---|
| 小学1年生 | 8冊 | 1,803g |
| 小学2年生 | 5冊 | 1,085g |
| 小学3年生 | 10冊 | 2,643g |
| 小学4年生 | 7冊 | 1,993g |
| 小学5年生 | 12冊 | 3,240g |
| 小学6年生 | 9冊 | 2,961g |
| 中学1年生 | 15冊 | 6,801g |
| 中学2年生 | 9冊 | 3,370g |
| 中学3年生 | 6冊 | 3,008g |



中学1年生の教科書の合計重量は7キロ弱!
郵送料は結構な額になりますね。
郵送手配の方法は、各大使館・総領事館によってまちまちです。
- 郵便局で、教科書の大きさ・重量に合ったを箱や封筒を購入し、大使館・総領事館に送付する
- 大使館・総領事館が配送を委託している業者に連絡する
- FedExなどの宅配業者のサービスを利用する
各大使館・総領事館の指示に従いましょう。
「いついつまでに受領しなければならない」という受領期限が設けられていて、その期限までに受領しないと申込がキャンセルになってしまう場合があるので注意しましょう。
大使館・総領事館での教科書申込時期を逃してしまった場合の教科書入手方法
「うっかりして教科書の申込時期を逃してしまった!」
「教科書の申込時期にまだここに住んでいなくて申し込んでなかったけど教科書が必要になった。」
という人は、次の2つの方法で教科書を入手することができます。
- 大使館・総領事館や、通う予定の学校(日本人学校や日本語補習校など)にキャンセル分がないか尋ねてみる。
- 大使館・総領事館を通じて、日本の海外子女教育財団宛に「教科書追加送付申請」を行う。
詳しくは別記事にまとめていますので、参考になさってください。
最後に
海外に住む日本人のお子さんでも、条件を満たしていれば受けられる日本の教科書の無償配布。
お子さんが日本人学校や日本語補習校などに通われている場合は、学校が申込・受領の取りまとめをしてくれるので楽です。
一方、個人で申し込む場合は、もらい損ねないよう、申込と受領のタイミングをきちんと把握し、申込を行う必要があります。
ところで、我が家の子供たちの教科書を見て気が付いたのですが、裏表紙にこんな記載があります。
この教科書は、これからの日本を担う皆さんへの期待をこめ、税金によって無償で支給されています。大切に使いましょう。
海外に住んでいても、日本国民の皆さんの税金で、日本の教科書が無料でいただけることは本当にありがたいです。
子供たちがこれから大きくなって、どんな形で日本と関わり、どんな形で貢献できるか未知数ですが、しっかり教科書を活用させていただかねば、と思います。
海外におられるお父さん、お母さん、これからもお子さんの日本語教育頑張りましょうね(自分にも言い聞かせています。笑)。

